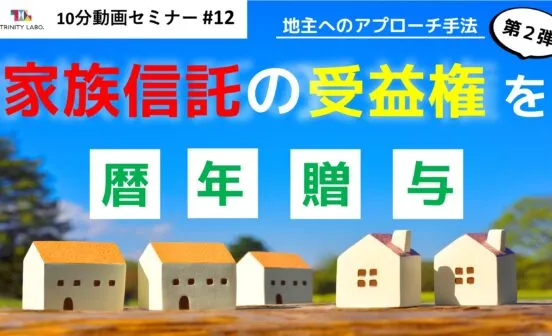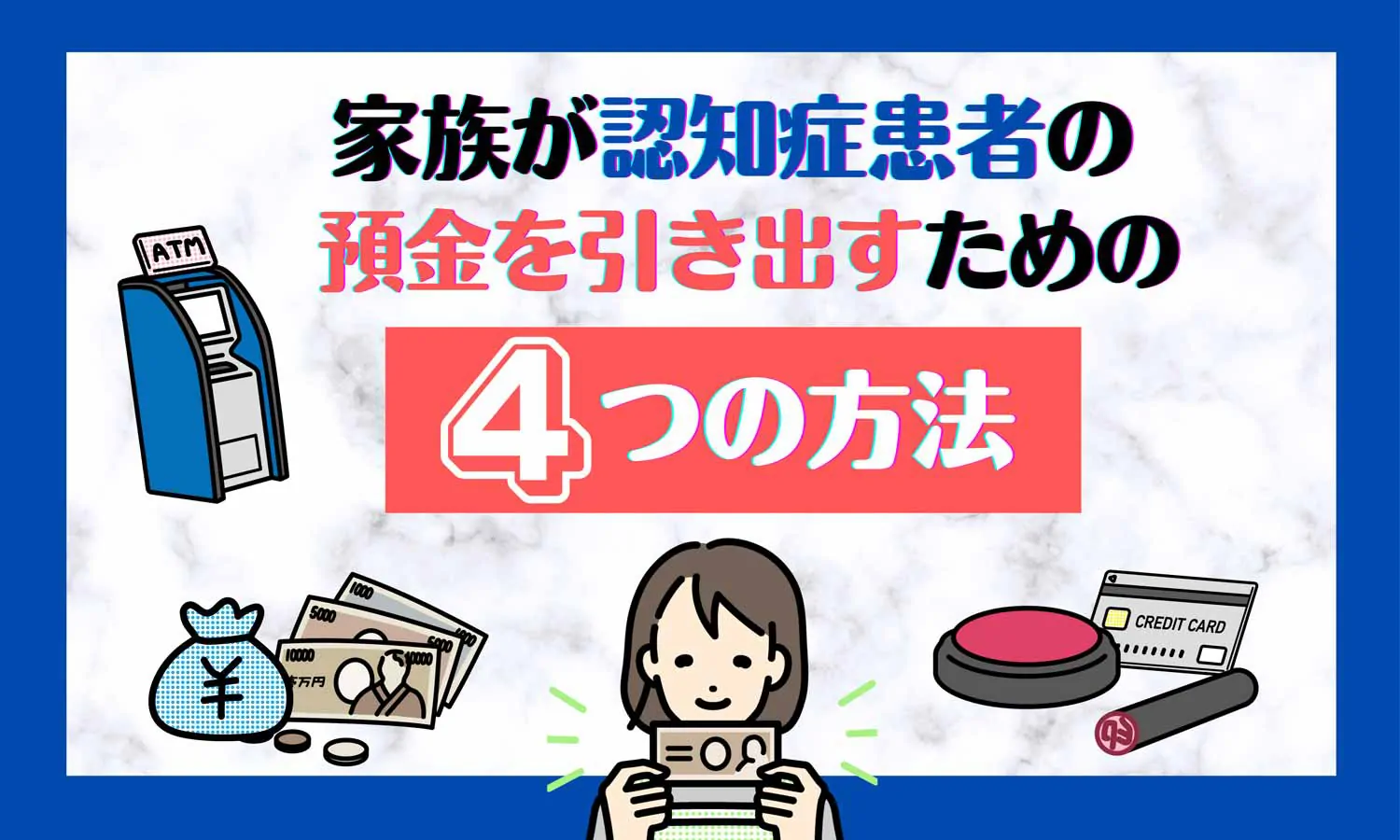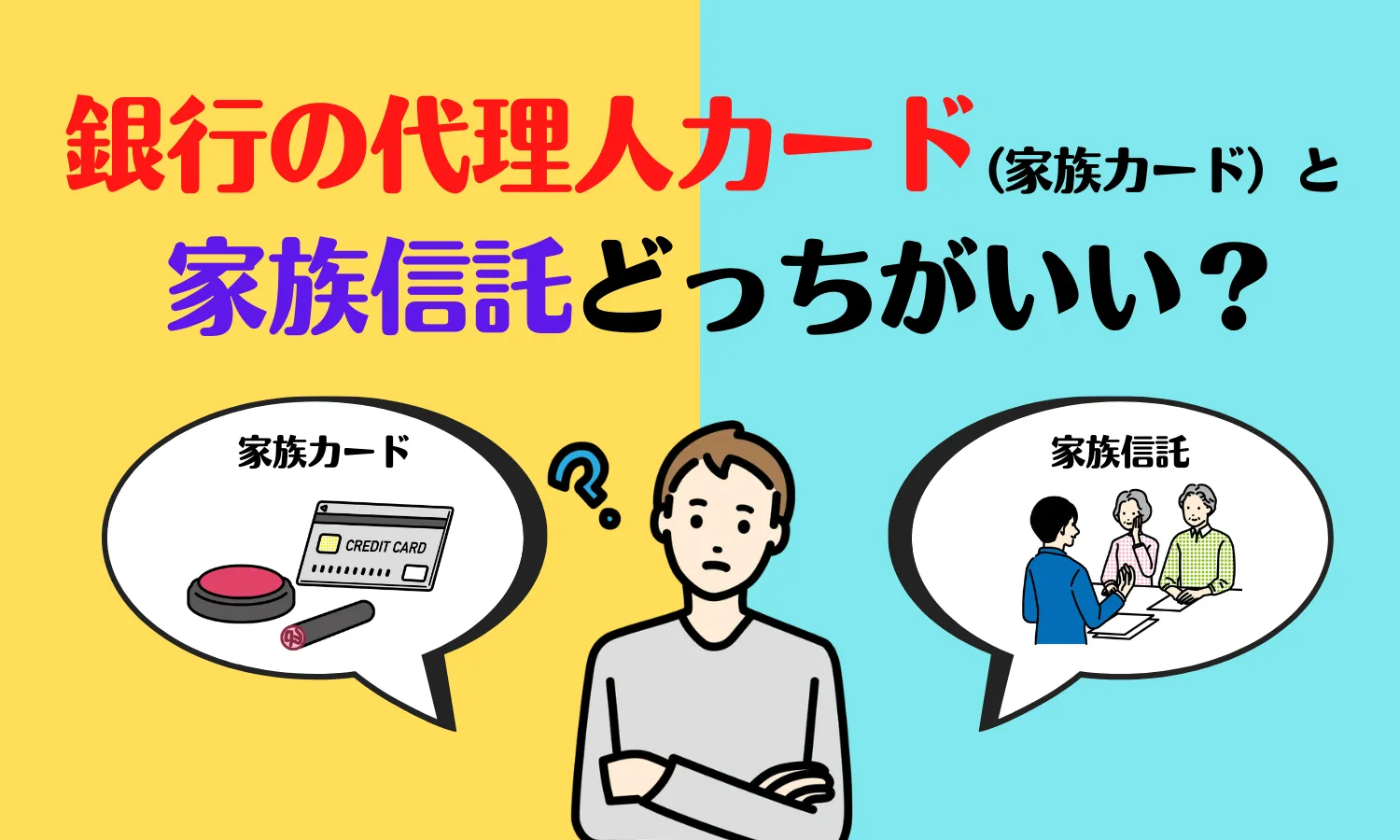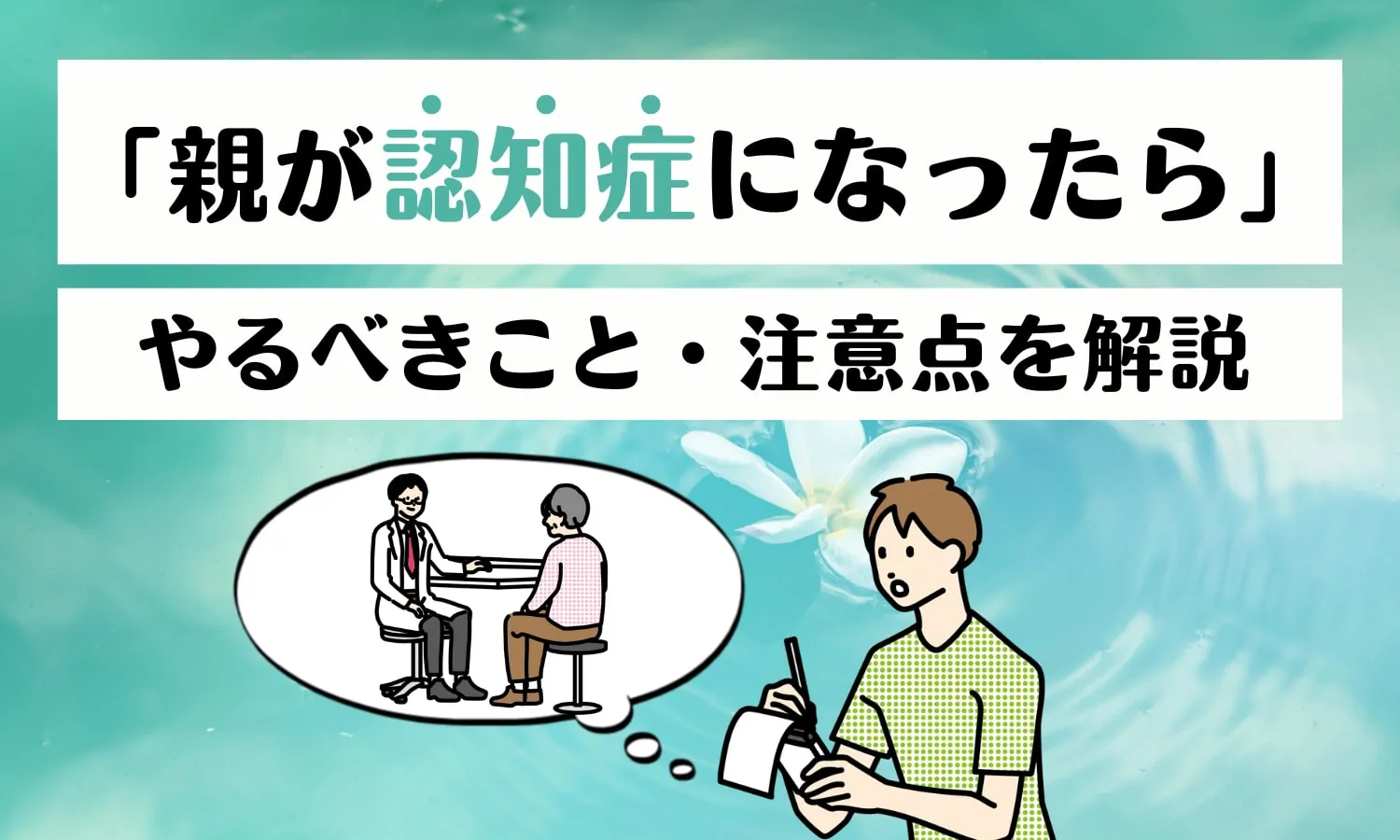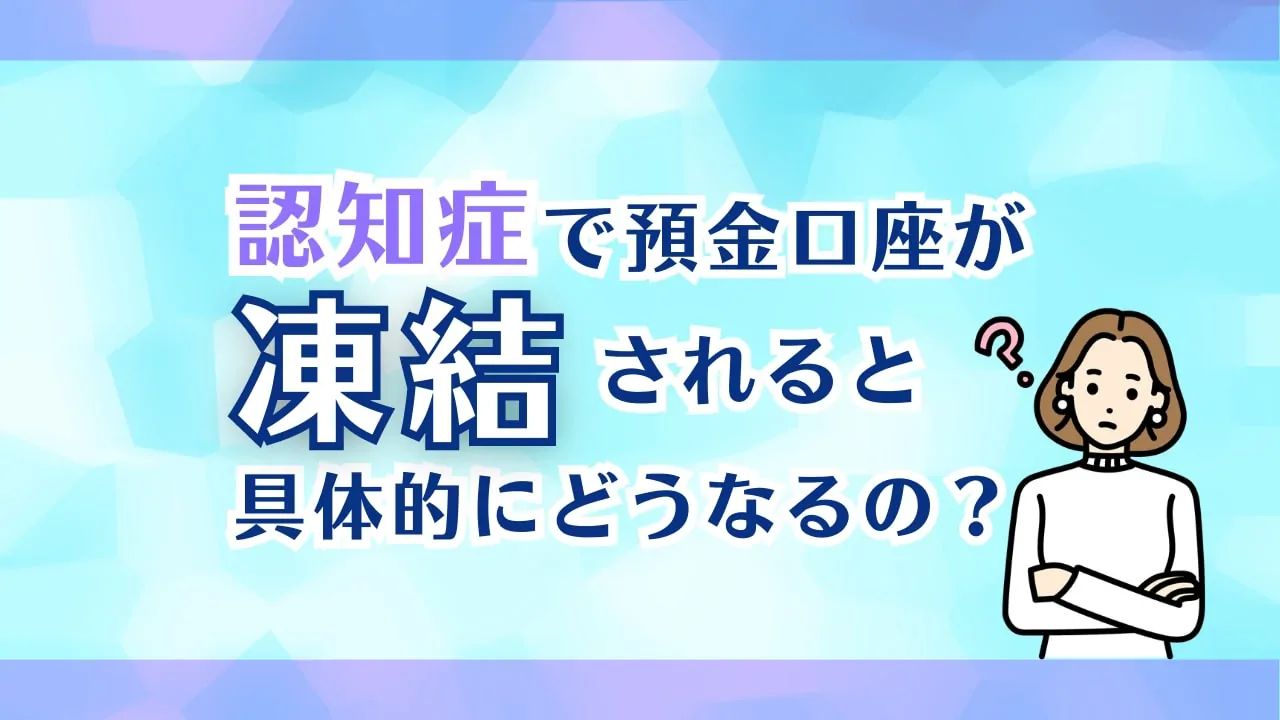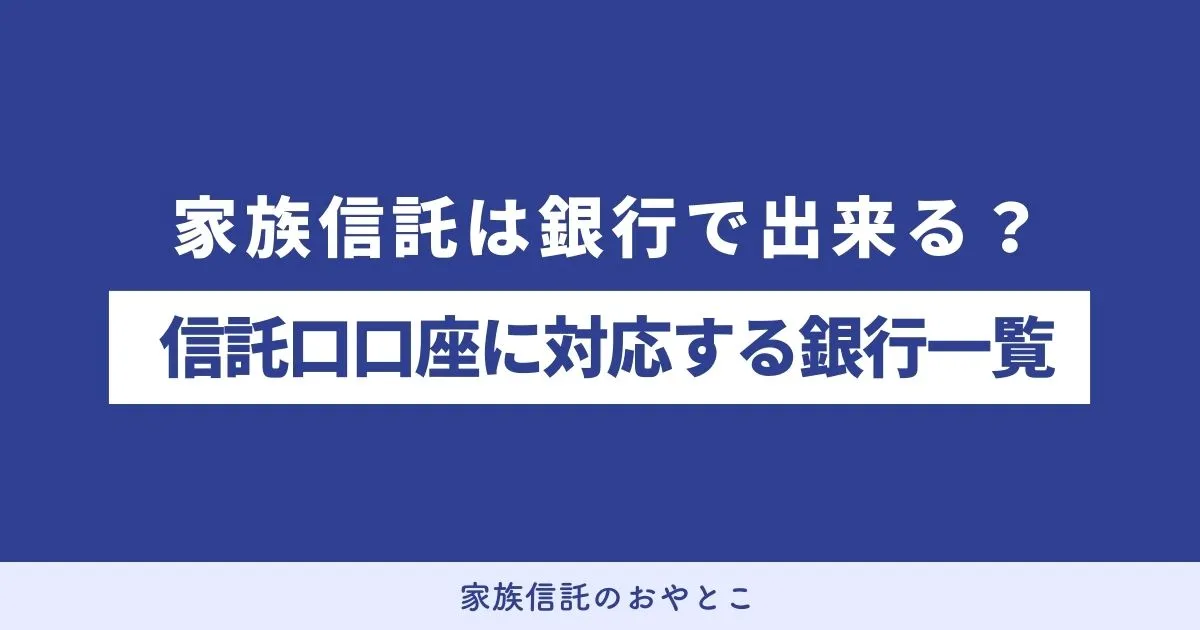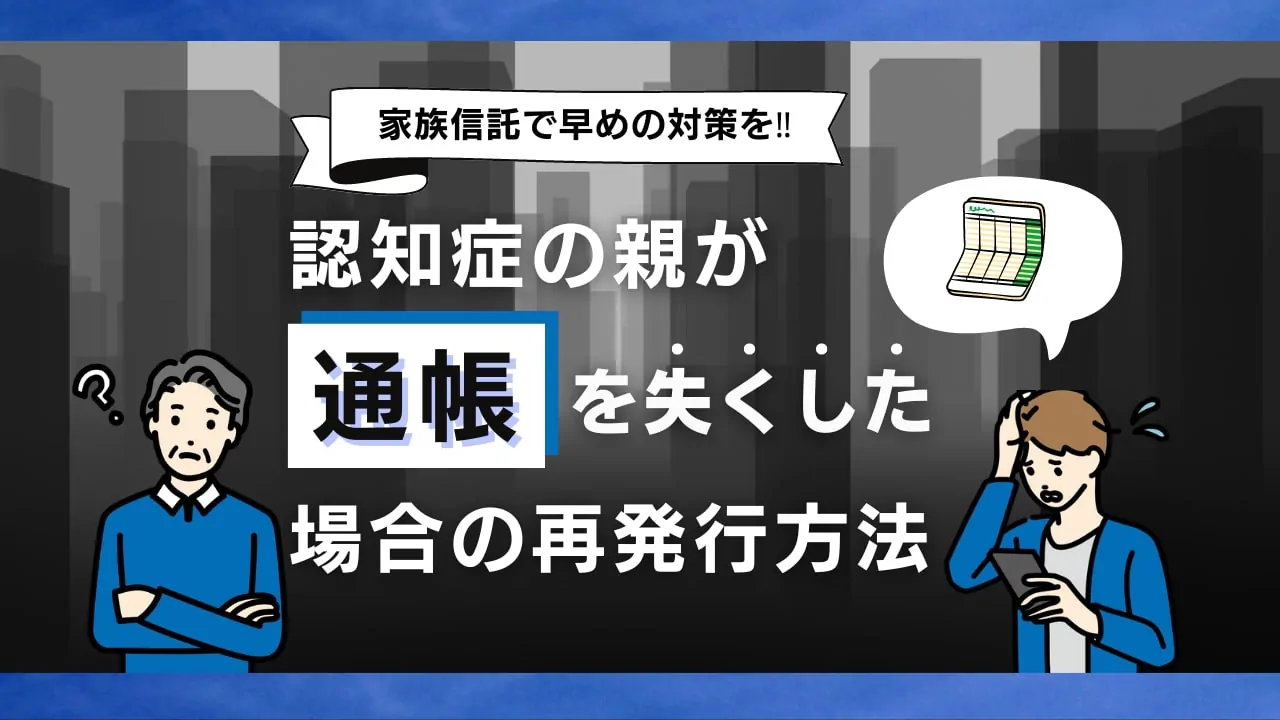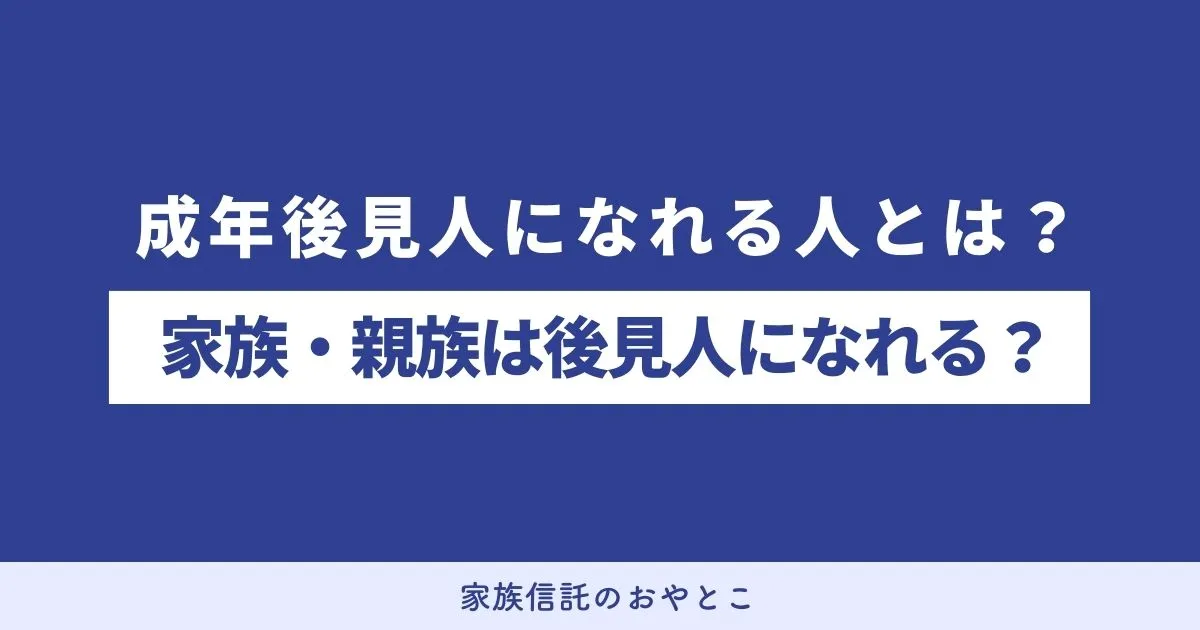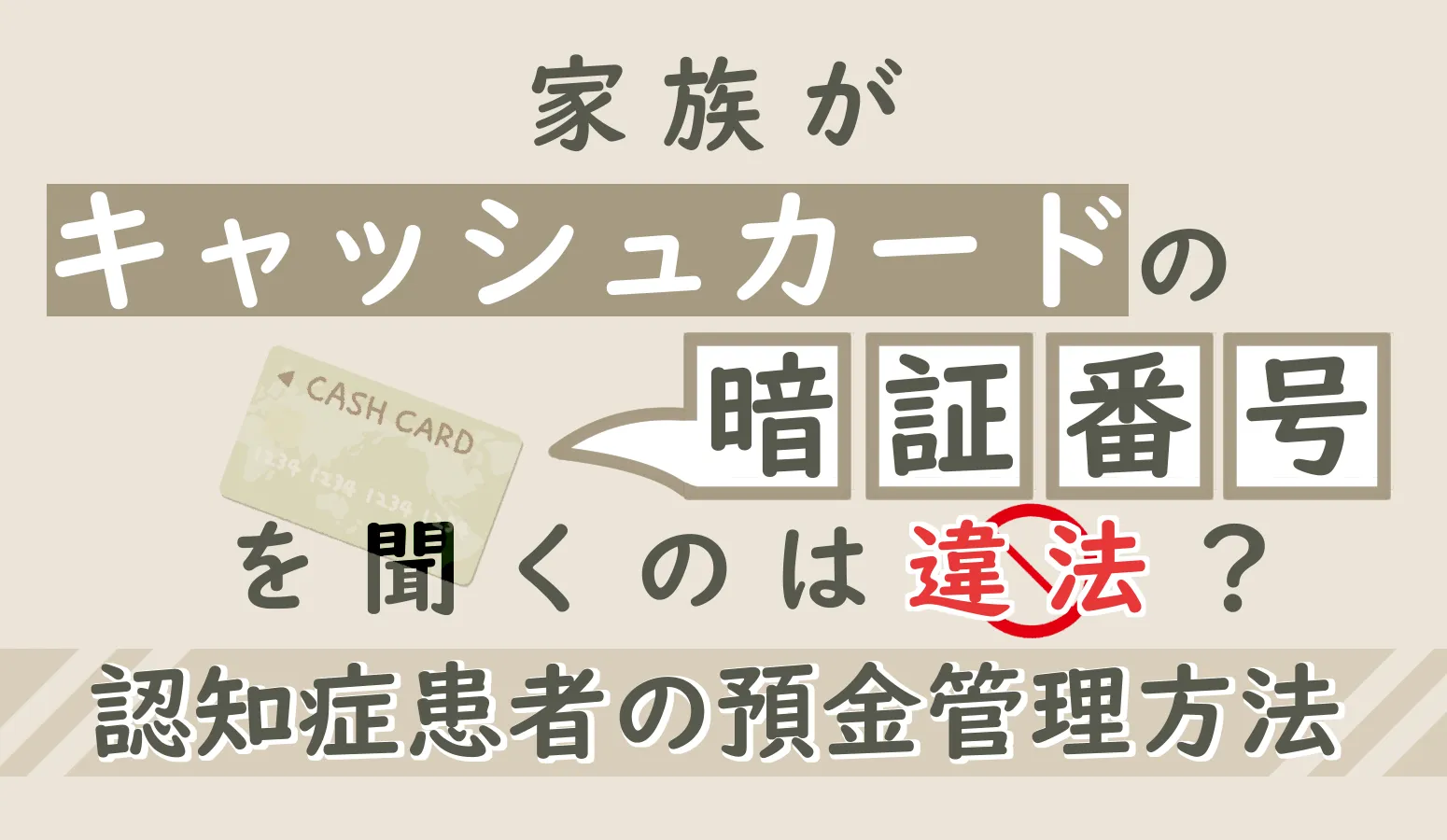今回は【家族信託×節税スキーム】として受益権の暦年贈与をテーマにお話をします。
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは一般的な相続税対策の一種ですが、その暦年贈与と家族信託がどのようにクロスオーバーしていくのでしょうか。
相続対策でよく利用される「暦年贈与」を家族信託を用いた場合について説明の上、後半で、その注意点について解説します。
家族信託とは?についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
【参考記事】
・家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを説明します
・家族信託は危険?実際に起こったトラブルや回避方法
・家族信託に必要な費用を解説!費用を安く抑えるポイント
・家族信託で気をつけるべきデメリット・注意点10選
・認知症になると銀行口座が凍結される理由と口座凍結を防ぐ方法
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する
目次
不動産を暦年贈与した場合のコスト
節税目的の「暦年贈与」は、一年間(暦年)の贈与額が1人あたり110万以下であった場合に贈与税がかからないという税の仕組みを使った贈与の方法です。
数年に分けて長期的に繰り返し贈与します(連年贈与は不可)。
しかし、暦年贈与にはコストがかかるという特徴があります。相続税対策の必要な地主Aさんの例を考えてみましょう。
【地主Aさんの事例】
地主Aさんは土地等の不動産を複数所有していますが、現預金はそれほど所有していません。不動産の権利を少しずつ移転する方法で、身内に暦年贈与を検討しているところです。
Aさんが一般的な暦年贈与を検討した場合、以下のようなコストがかかります。
《不動産の暦年贈与にかかるコスト》
② 不動産登記にかかる登録免許税(2%)
③ 司法書士費用
この事例の場合、これらのコストは贈与の年ごとに必要となります。
受益権の暦年贈与であれば、コストがほとんどかからない
一方、地主Aさんが「家族信託」を利用した場合はどうなるのでしょうか?
【事例】委託者:地主Aさん(父)、受託者:子Bさん
父が所有する不動産を子に信託し、受益者を父として信託契約を締結します。
不動産の名義は子に移転し、委託者である父Aさんは利益を受け取る「受益権」を取得することになります(自益信託)。
これにより、Aさん所有の不動産からの収益が「受益権」に変化しました。将来、Aさんの意思能力が低下したとしても不動産の運用は子Bさんに任せているので安心です。
また、「受益権」は贈与したり譲渡したりすることができるため、他の受益者に渡すこともできます。収益の活用法が広がった状態になりました。
[1]不動産からの収益が「受益権」に変化
信託不動産からの収益が「受益権」に変化し、暦年贈与したい人を「受益者」の1人に加えることで利益を渡すことができます。
コストをかけずに暦年贈与をすることが可能となるのです。
不動産を通常通り所有したまま、その収益を暦年贈与しようとしても、所有者Aさんの健康面に問題が生じたり、意思能力が低下した場合には暦年贈与はストップしてしまいます。
そのような事態を防ぎ、贈与をする方法として、家族信託が利用できるのです。
現段階では収益のみが贈与され、不動産本体については相続時に引き継がれることになります。
[2]家族信託で暦年贈与した場合のコスト
家族信託の受益権の暦年贈与であれば、コストもほとんどかかりません。
①贈与契約書
②確定日付のある受託者の承諾書
③確定日付の取得費用:1通700円
このように低コストでの実行が可能です。
※これに加えて、家族信託の組成費用は別途必要となります。
[3]受益権の評価
受益権の評価については、相続税法9条の2により相続税評価(固定資産税評価額)とされます。
したがって、信託不動産は通常どおり相続税評価にて評価すればよいということになります。
[4]相続税よりも税率が低いため多めに贈与しておく方法も
また、暦年型の贈与は、年110万円以下限定ではありません。
例えばこの信託契約で1暦年に400万円程度の贈与をしても、最終的な相続税の税率と比べると、実質の負担税率はあまり高くならないという利点があります。
(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合)
不動産の収益に変動がある場合など、多めの贈与をすることで先に納税(贈与税)しておくという方法も選択肢に入ります。
[5]受託者に頼んで暦年贈与はできないの?【注意】
上記のように家族信託を利用して暦年贈与する方法が分かりました。
しかしここで、家族信託により受託者に財産の管理処分を依頼しているわけですから、暦年贈与についても受託者に依頼できるのでは、と考えることもあるでしょう。
一般的な暦年贈与については、贈与を継続している途中で贈与者が認知症が進行したために贈与のスケジュールが止まってしまう、というケースもよくあります。
家族信託を利用して、贈与者(委託者)の意思能力が低下した後も、受託者に頼んで実行してもらうことはできるのでしょうか。
【受託者に暦年贈与を委託する行為は不可】
この方法については取扱い不可だと考えてください。
信託契約で「受託者」の立場は「受益者のために限定して」財産の管理・処分をすべき立場になります。
そのため受益者以外の人のために信託財産から贈与することはできないのです。
忠実義務(信託法第30条)違反になりますし、税制上否定され、課税対象となる可能性が高くなります。
そのため暦年贈与を希望している場合、受託者に贈与手続きを依頼するのではなく、子や孫を受益者に追加する(子や孫に受益権の一部を渡す)方法で信託契約を結ぶことになるのです。
受益権の贈与をする際の注意点
ここまで受益権の贈与の有効性についてお話してきましたが、冒頭でお伝えしたように、家族信託を利用した暦年贈与(受益権の贈与)には注意点があります。
移転登記のコスト
受益権の贈与の段階では、不動産取得税や登録免許税等の移転コストはかかりませんが、信託終了時には相続が発生するため、これらの移転登記の費用が必要になります。
負担付贈与とみなされるケース
抵当権が付いた不動産からの受益権を贈与する場合、債務を伴う「負担付贈与」とみなされると課税対象となる場合があります。
負担付贈与とみなされると、評価額は時価での評価(有利な固定資産税評価額ではなく、取引価額)となり、また、譲渡所得税がかかってしまう場合があります。
通常は贈与を受けた「受贈者(信託の受益者)」のみが贈与税の課税対象となりますが、負債等のある資産家らの贈与で「負担付贈与」と判断されると、「贈与者(信託の委託者)」への贈与ありとして贈与者も課税される可能性があるのです。
受益権の贈与については信託税務のチェックを
受益権の贈与は、前述[2]の通り2つの書類を作成すれば簡単に贈与設定できますが、実行にあたっては上記のような注意点もあり、課税面の検討が必要となります。
そのため、信託契約を作る段階から家族信託に精通した専門家へ相談されることをお勧めします。
まとめ
通常の暦年贈与はコストがかかりますが、家族信託を行って「受益権の暦年贈与」をした場合はコストを抑えることができるため、地主さんなどの相続税対策が必要な方におすすめです。
ただし、注意点として
- 受益権の贈与の段階では、不動産取得税や登録免許税等の移転コストはかからないが、信託終了時には、これらがかかってくる
- 抵当権付の不動産にかかる受益権を贈与する場合は、「負担付贈与」とみなされ、「時価での評価」となり、また「譲渡所得が課税」される場合がある
という2点があげられます。
実行にあたっては慎重な検討が必要となりますので、ぜひ家族信託の専門家へご相談ください。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する