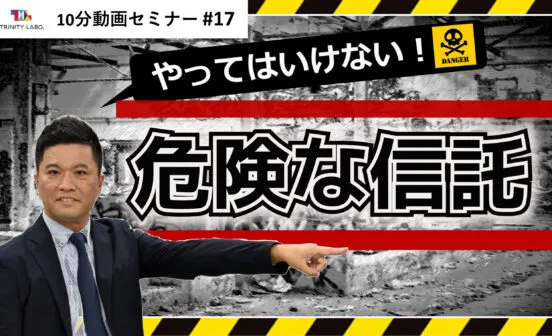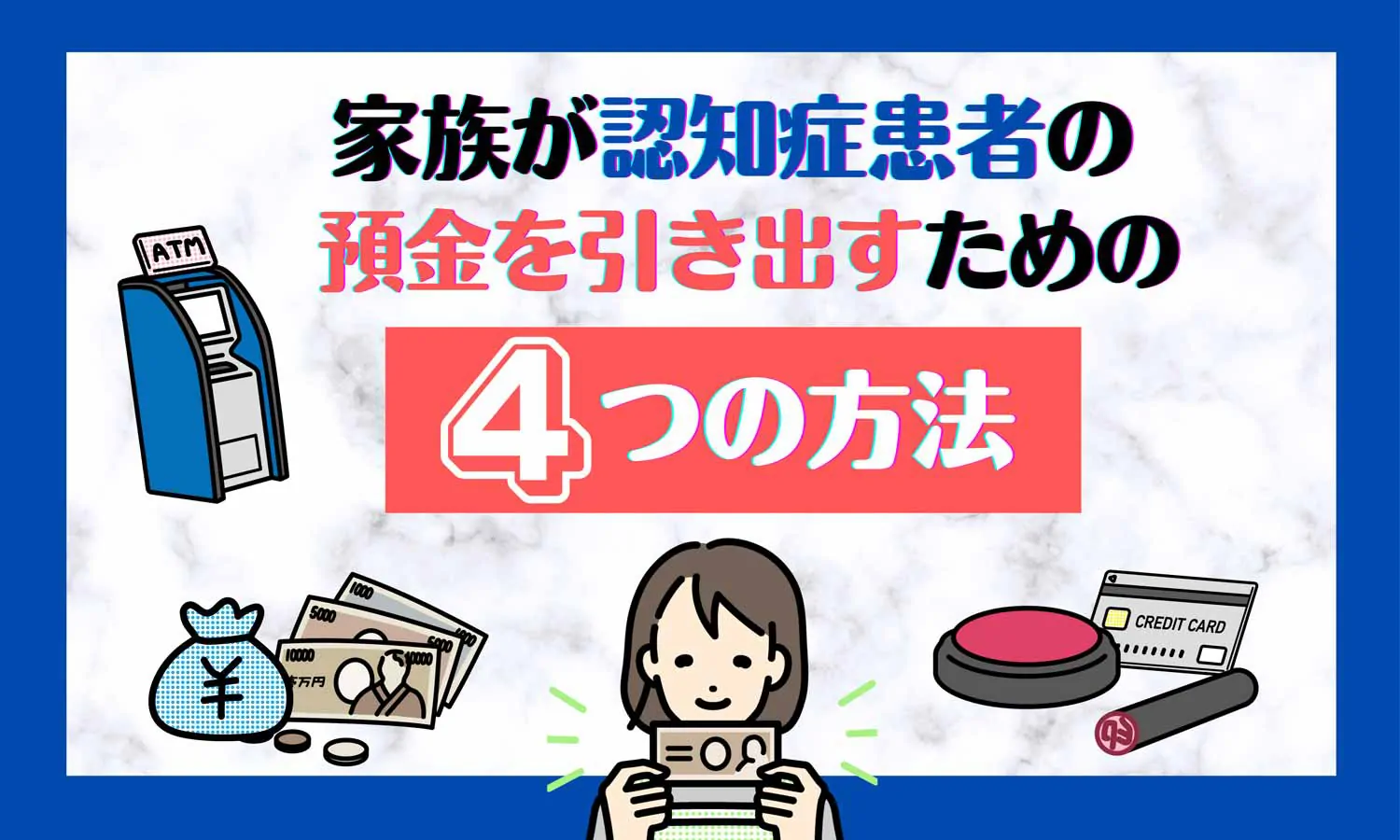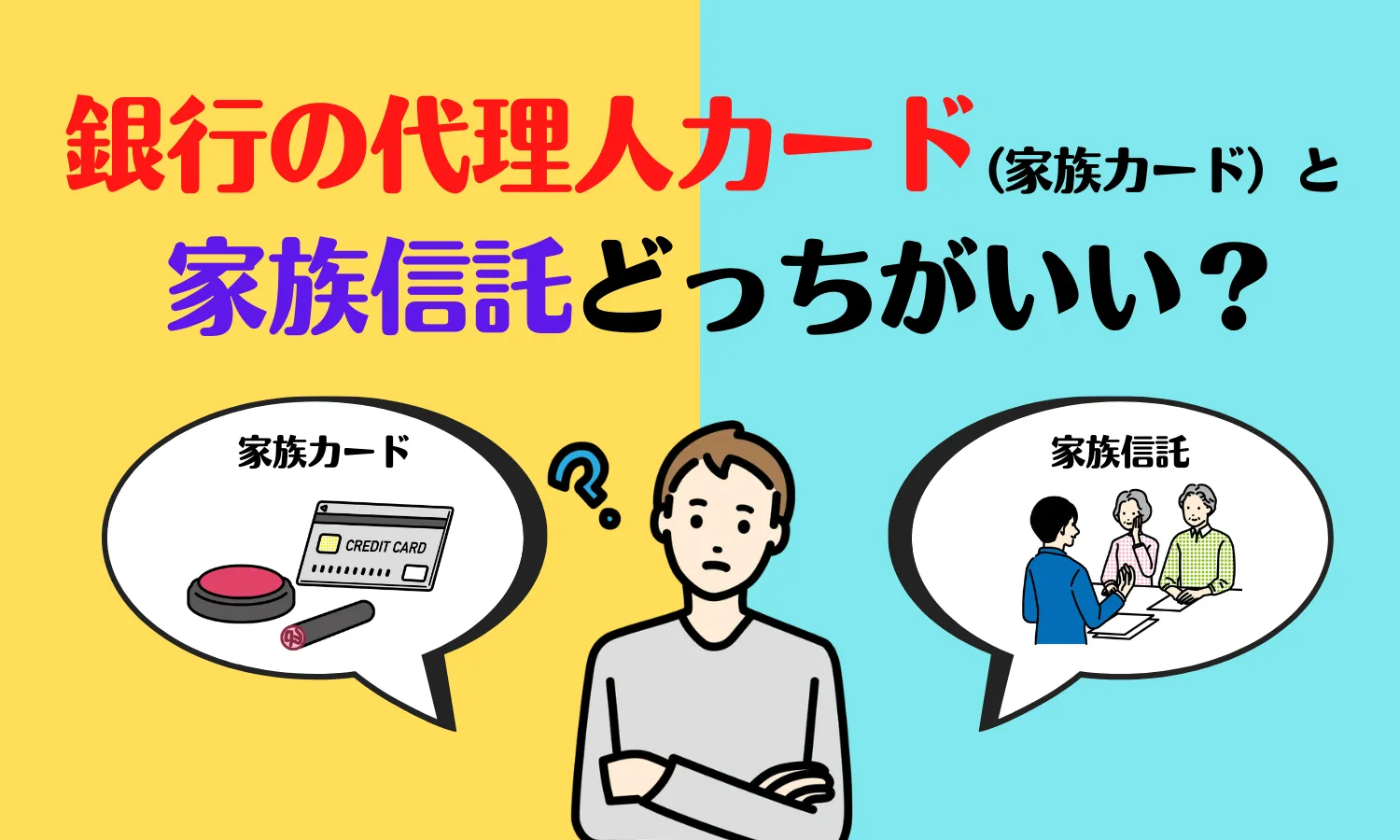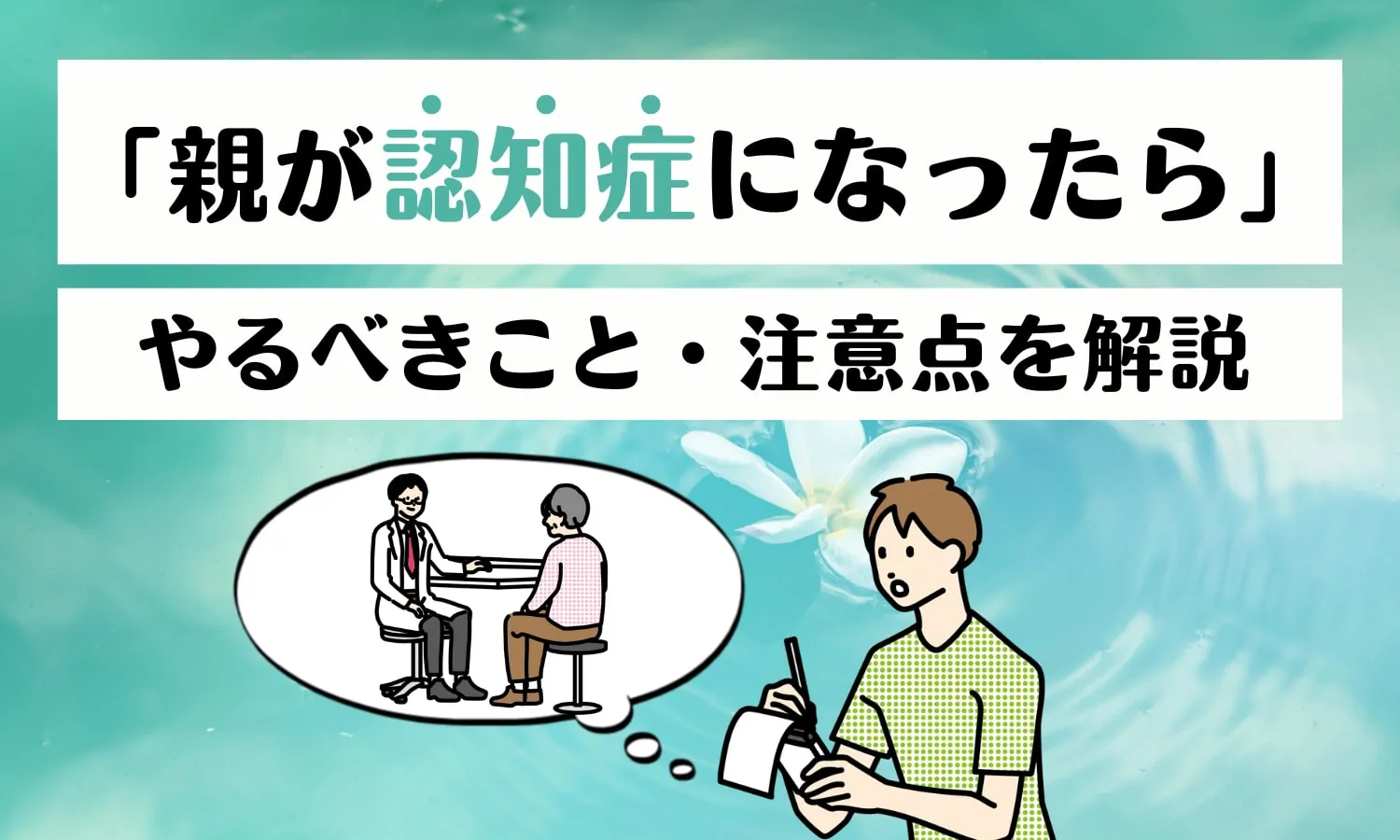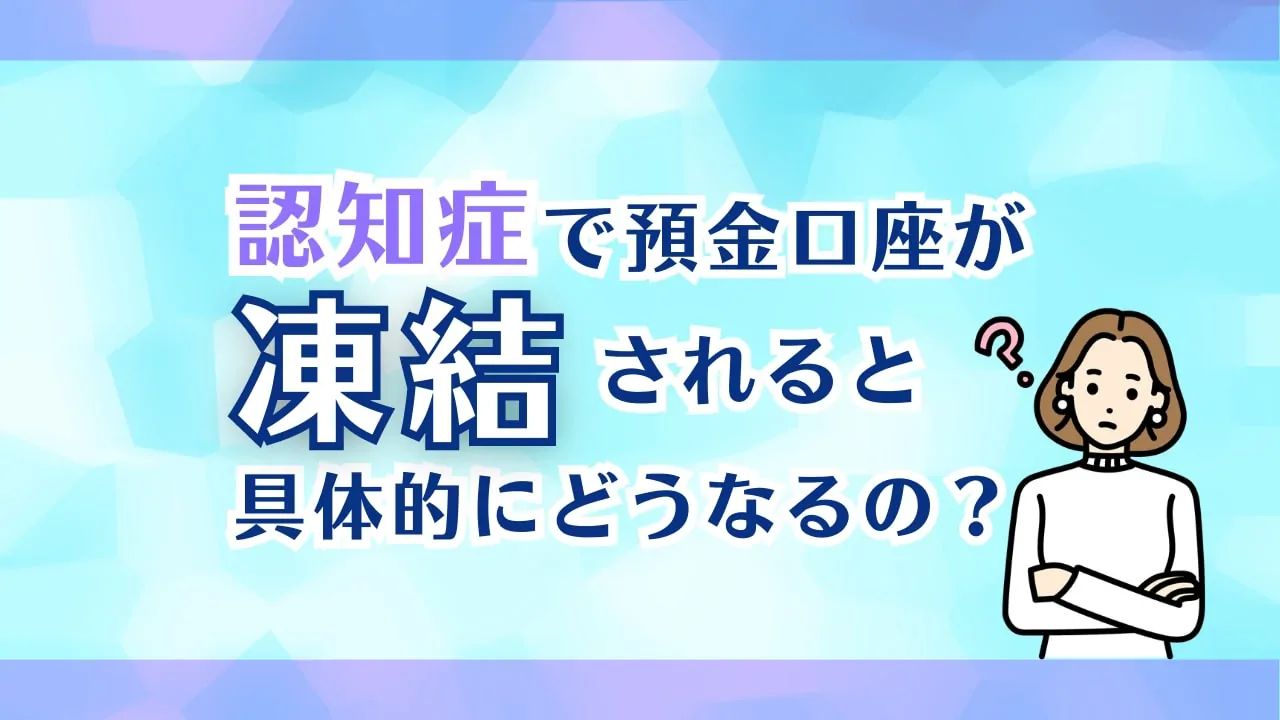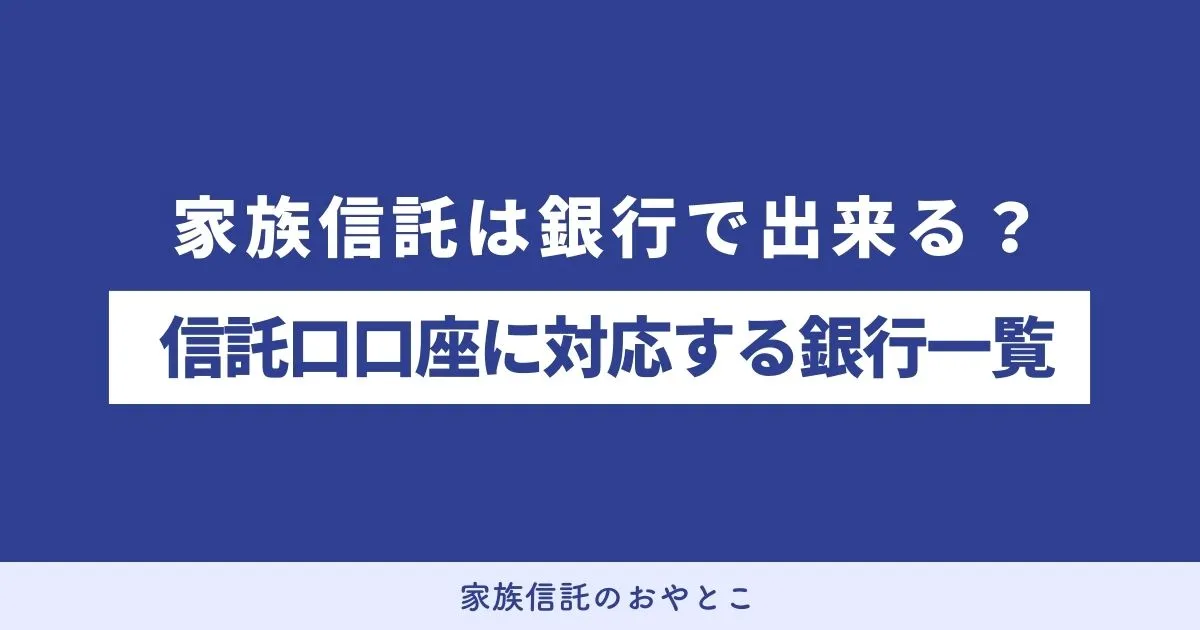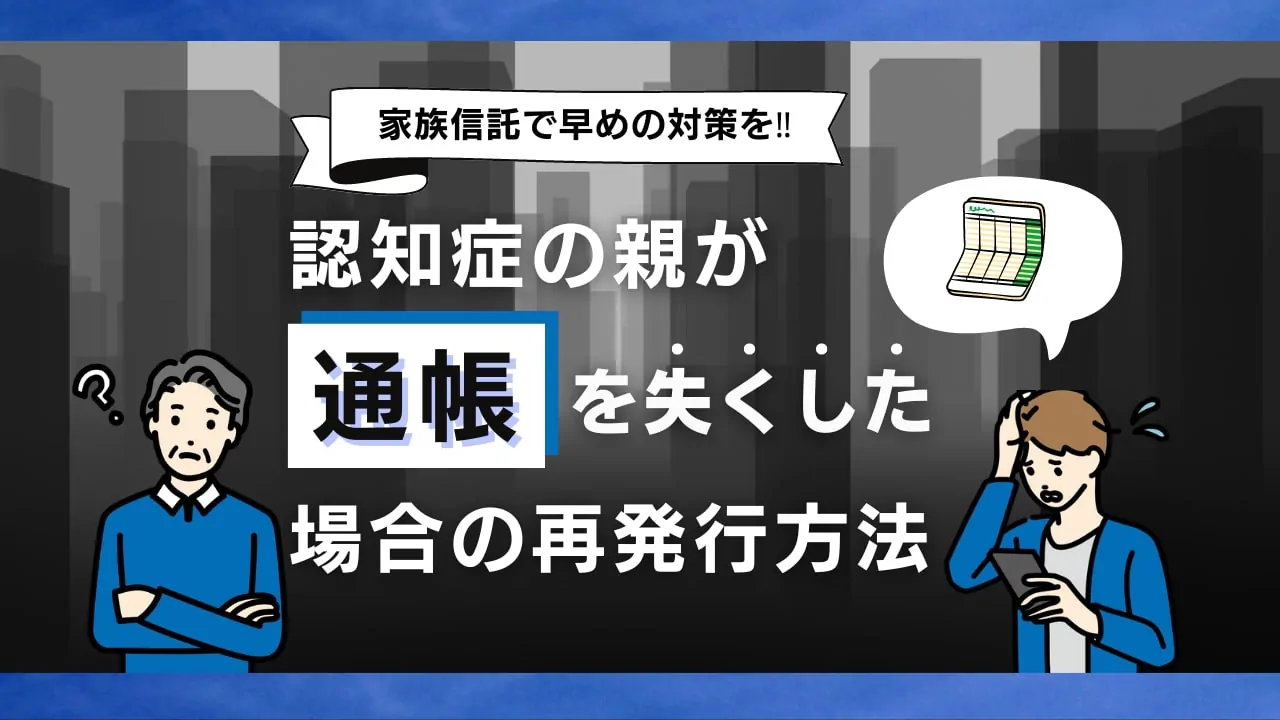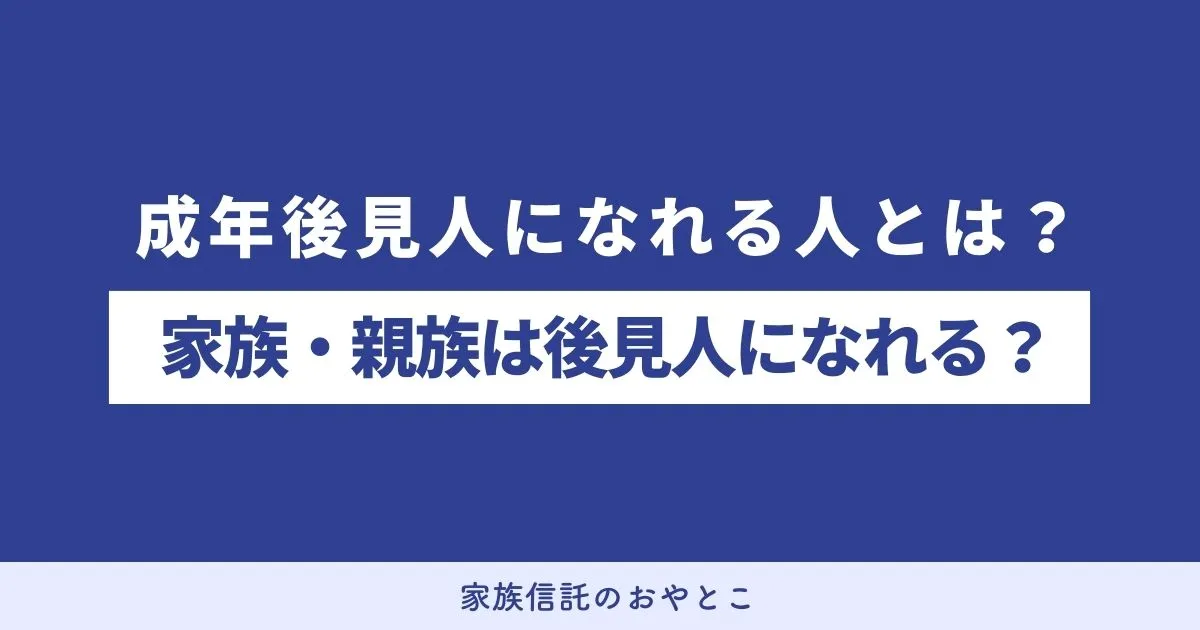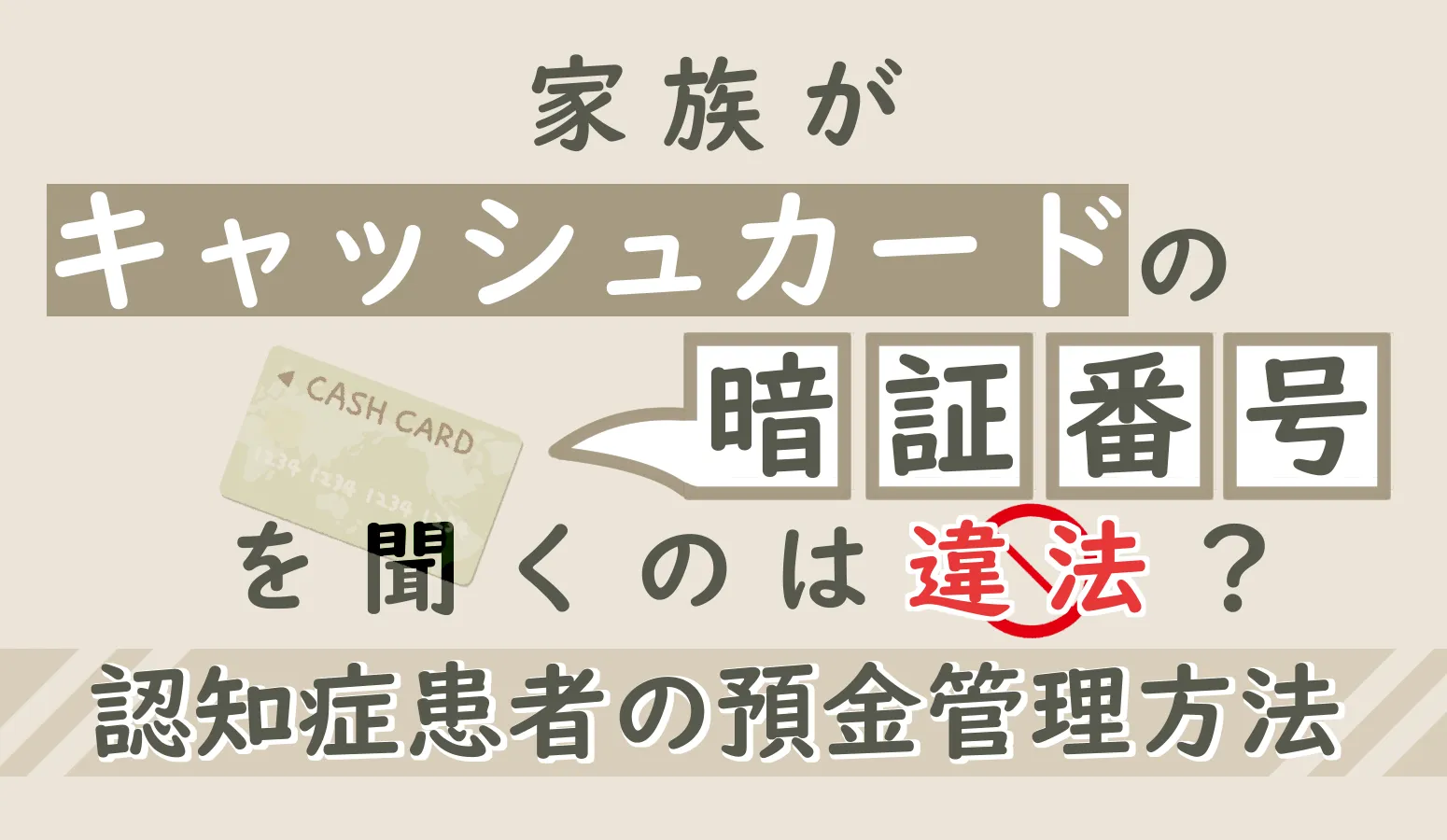家族信託は手軽に家族間で信託契約をして財産管理を依頼することのできる便利な制度です。
ただし、信託法に基づいて利用するため、内容によっては思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。
例えば、専ら「受託者の利益」を図る目的の信託を組成してしまうと、信託法上、無効となってしまいます。無効とは恐ろしいですね。
「専ら受託者の利益を図る目的の信託」とはどのような内容なのか、解説します。
【参考記事】
・家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを説明します
・家族信託は危険?実際に起こったトラブルや回避方法
・家族信託に必要な費用を解説!費用を安く抑えるポイント
・家族信託で気をつけるべきデメリット・注意点10選
・認知症になると銀行口座が凍結される理由と口座凍結を防ぐ方法
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する
目次
契約が無効?「受託者の利益を図る目的の信託」とは
無効になる信託契約とは、信託法で「専ら受託者の利益を図る目的の信託」と規定されています。
まず信託法について確認しましょう。信託契約がどのような契約なのか、信託法2条に記載されています。
信託法
信託とは、受託者が一定の目的に従って、財産の管理・処分等をする契約です。受託者の目的には例外があり、専ら受託者自身の利益を図る目的の場合は、信託の定義からは外れることになります。
条文の「特定の者」は「受託者」を指し、信託とは受託者が一定の目的に従って、財産の管理、処分等をすべきものとすることであると書いてあります。
ポイントは「一定の目的」のところにカッコ書きがあり、「専らその者の利益を図る目的を除く」とされている点です。
「その者」というのは「特定の者」である「受託者」を指していますから、「専ら受託者の利益を図る目的を除く」つまり、その場合、信託の定義から外れる、という記載になっています。
このことから、「受託者の目的を図る信託契約は無効」ということになります。
専ら「受託者の利益」を図る目的の信託の「該当・非該当」の判断について
受託者が自分のために利益を図る信託に該当するか・しないかについては、判断の難しい部分があります。
専ら受託者の利益を図る目的についての解釈の基準について、判例や通説は未だ確立されてはいません。
しかし、信託法の解釈においては、契約上の内容よりも、実質的な経済的効果があったかどうかで判断される傾向にあります。
では、専ら受託者の利益を図る目的の信託とは具体的にどのような信託なのか、具体例を挙げましょう。
【具体例】
委託者(兼受益者:自益信託)を父、受託者を長男として、土地を信託したと仮定します。土地の名義は信託財産として長男に変更されます。
長男がその土地の上に建物を建て、受託者として銀行から融資(信託内融資)も受けて土地建物に抵当権も設定されました。
建てた家には長男が住み、親子の間だからという理由で、特段、父親に賃料の支払いをしなかったとします。
最後に父が亡くなった場合、信託を終了させ、残余財産の帰属権利者も長男とする信託を組成したとしましょう。
このような信託は、誰のための信託でしょうか。
この信託によって、父は1円の利益も得ていません。
信託契約書の目的には、父の財産を管理するためと形式上書いてあるものの、実質は、すべて長男の利益のためになされた信託だと言えます。
この場合、専ら受託者の利益を図る目的の信託にあたってしまうのでしょうか。
解釈の基準については未確立
「専ら受託者の利益を図る目的」について、信託法の解釈においては、契約上の内容よりも、実質的な経済的効果があったかどうかで判断される傾向にあります。
信託法の権威であり、影響力のある東京大学大学院教授の道垣内弘人先生が『条解信託法』という書籍において言及しており、
「形式的に、受託者の行動を決定する基準としての「目的」が、自分自身の利益を図るべしとされているか否かではなく、その信託によって、当事者が達成しようとした実質的な経済的効果に照らして判断されるべきことになると思われる。」
(道垣内弘人、編著者 2017条解信託法 弘文堂)
としています。
つまり、今回の事例でも、実質的な経済的効果により判断されることとなれば、専ら長男の利益を図る目的との指摘を受け、信託契約が無効だと判断されかねません。
信託契約での形式的な規定や目的ではなく、実質的に誰が得をしたか、経済的効果により判断するという解釈です。
信託を組成する際には、このような判断を受けることのないよう、組成内容には注意しましょう。
まとめ
今回の事例でも、実質的な経済的効果により判断されることとなれば、専ら長男の利益を図る目的であり無効という判断を受ける可能性があります。
例えば、兄弟や相続人(相続人になる予定の親族)から無効を主張して争われる可能性もあります。
家族信託は受託者に権限が集中するという性質上、どうしても他の家族からの反感を買ってしまいがちです。
信託を組成する際には、このようなトラブルを誘発しないよう、信託の組成にはお気をつけください。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する