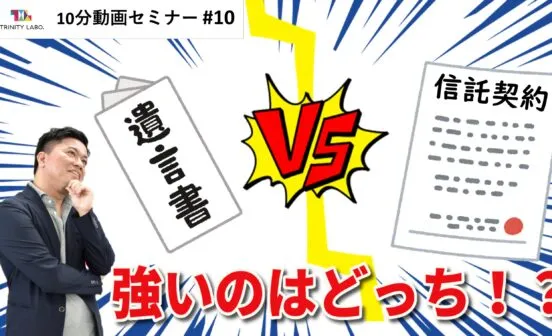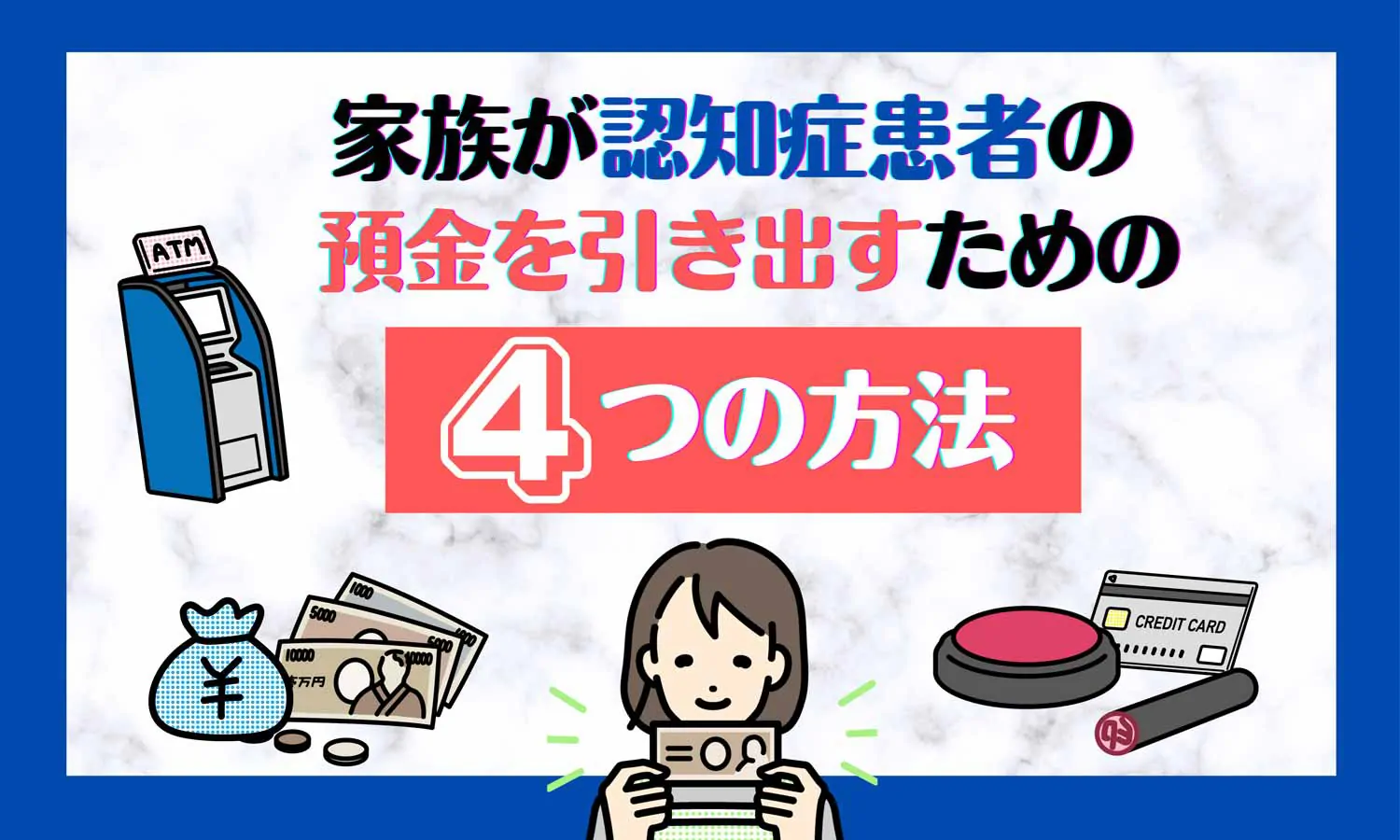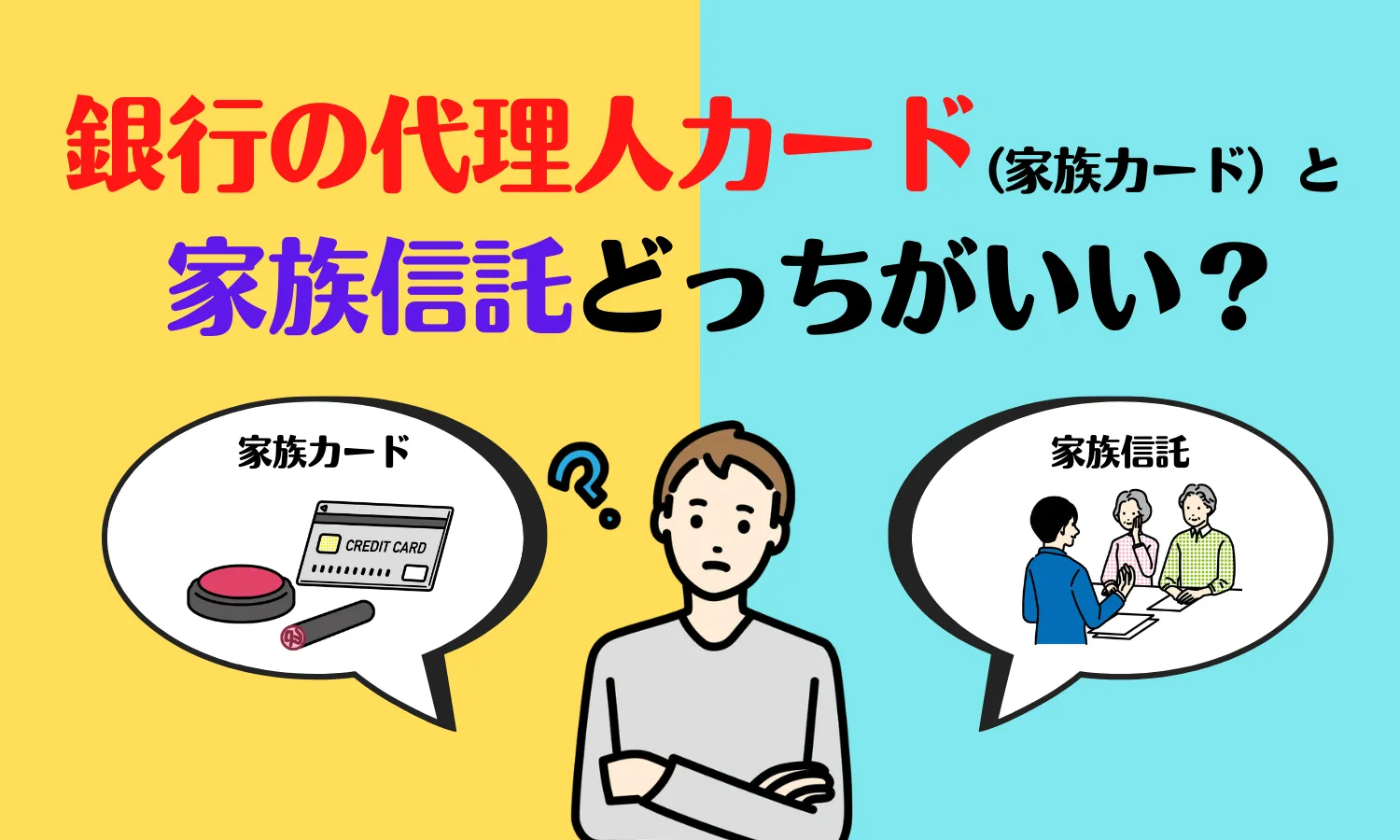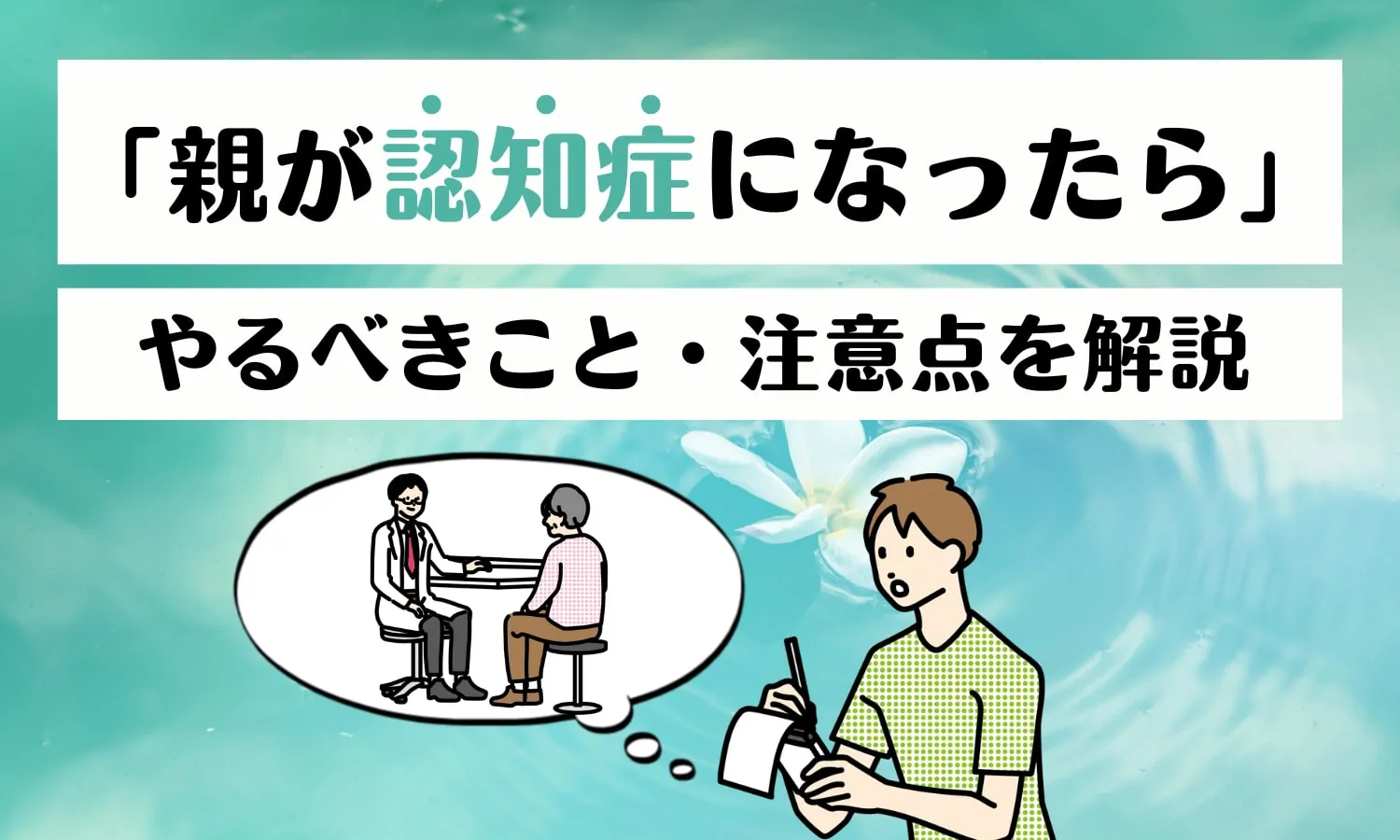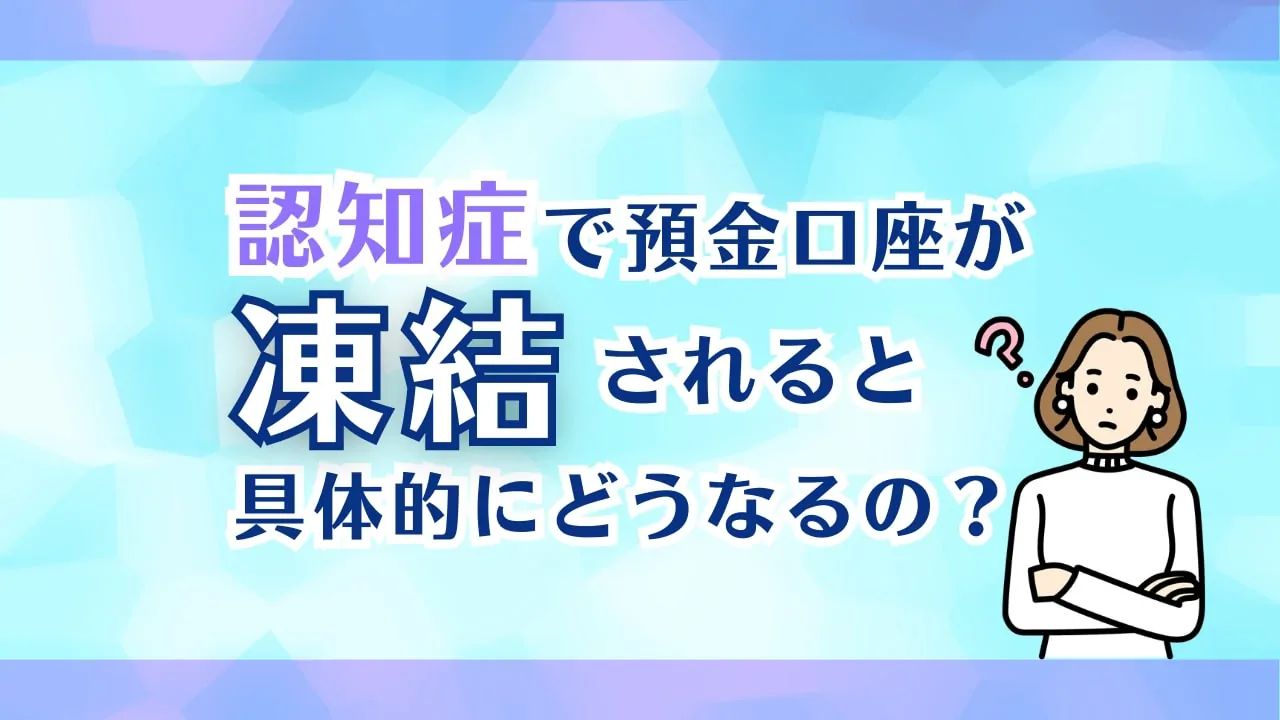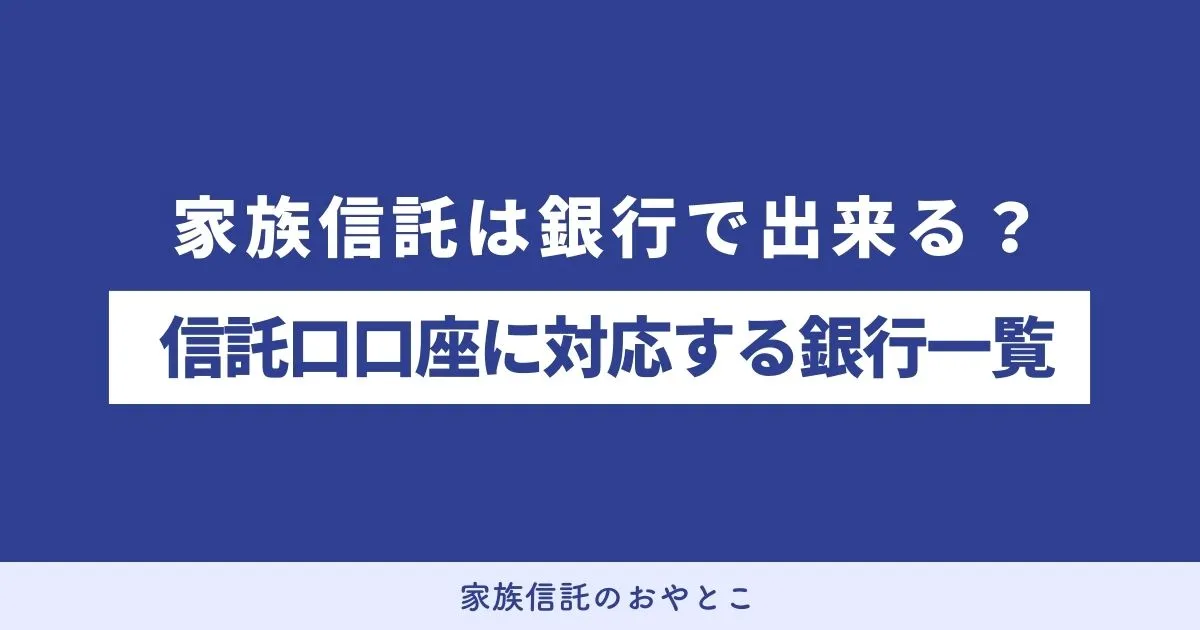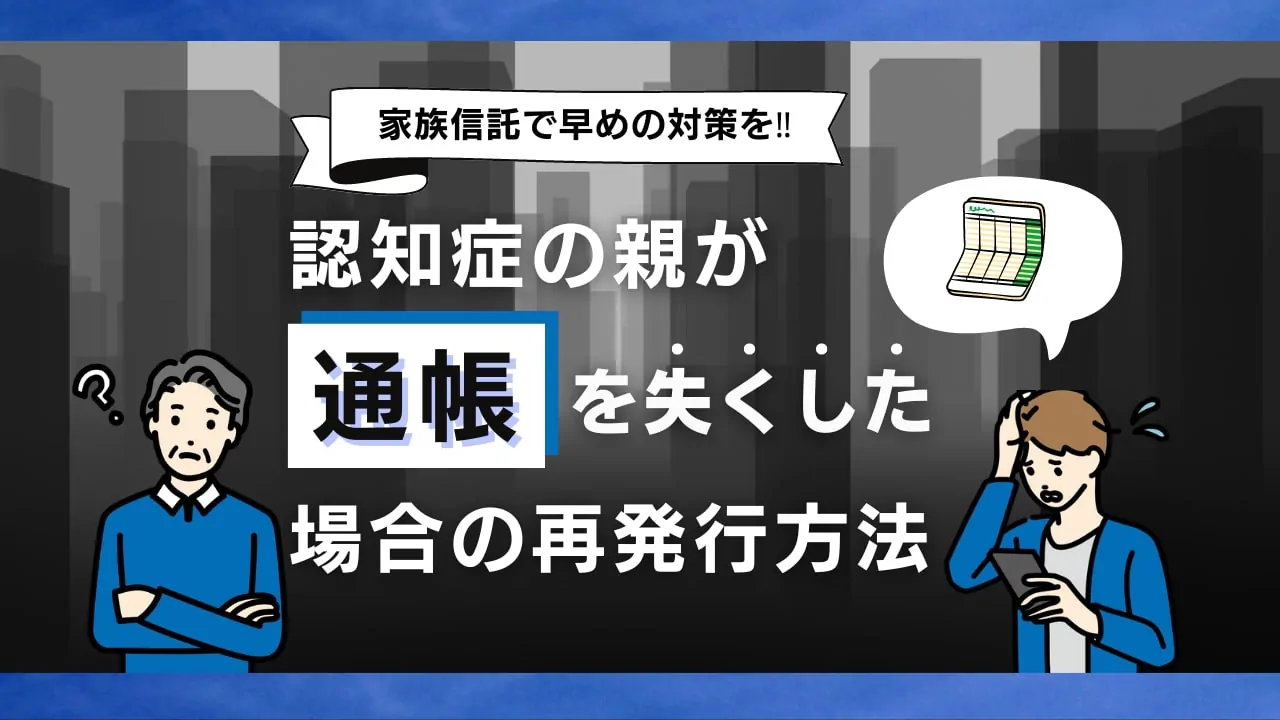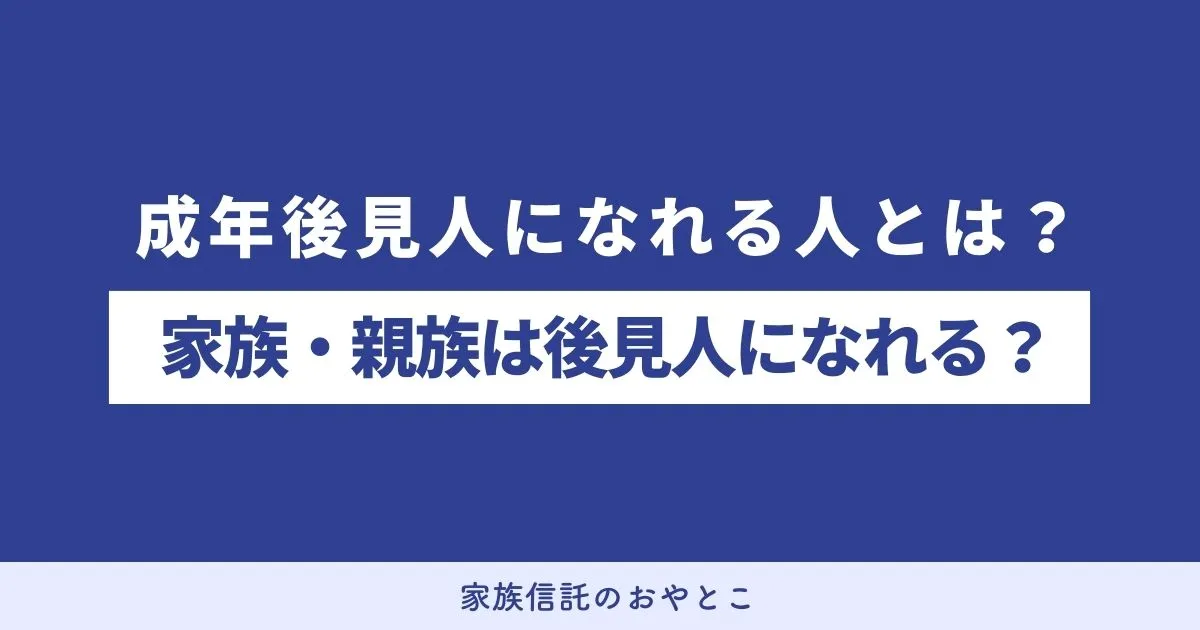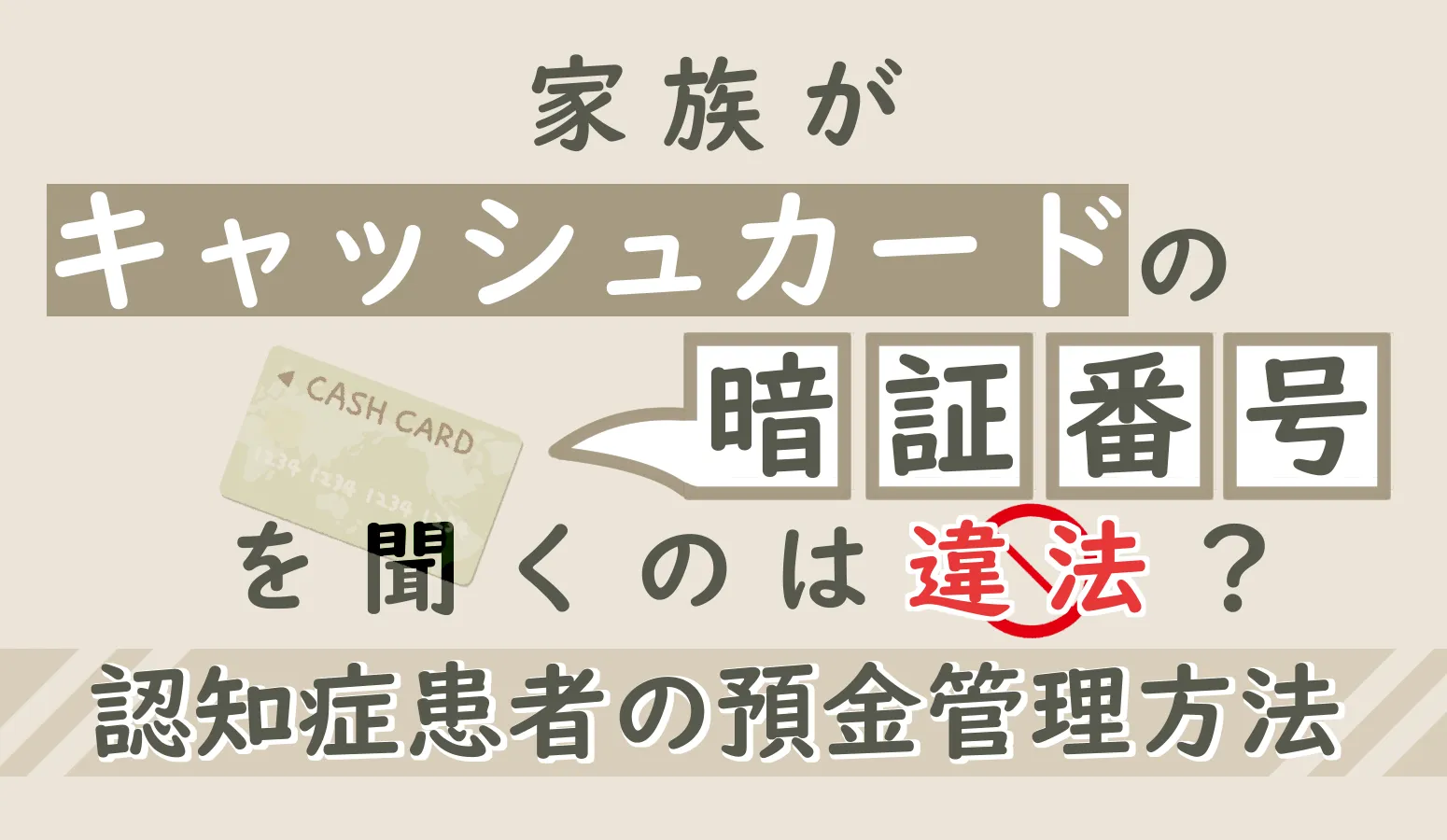家族信託には遺言的な機能もあります。
しかし家族信託と相反する内容の遺言が作成された場合、財産の帰属はどうなるのでしょうか?
この問題に迫っていきたいと思います。
【関連記事】
・家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを説明します
・家族信託は危険?実際に起こったトラブルや回避方法
・家族信託に必要な費用を解説!費用を安く抑えるポイント
・【家族信託の手続き方法まとめ】手続きの流れ・やり方を解説
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する
目次
家族信託は遺言の機能も持ち合わせている
ご存知のとおり、家族信託では、父の財産を子に信託することによって、子がその財産を管理することができるようになるため、父の認知症対策として有効です。
家族信託をした場合、父が亡くなった後の具体的な財産の承継方法は、家族信託の契約書の中で定めておくことができます。
つまり、家族信託は認知症対策だけでなく、遺言の機能も持ち合わせているのです。
遺言機能を持たせた信託を「遺言代用型信託」と呼びます。
遺言機能のある家族信託を活用して、終活準備や認知症の進行への備えを進めていきましょう。
【家族信託 v.s. 遺言】どちらが優先されるのか?
それでは、遺言と家族信託の両方を作成していた場合、果たしてどちらが優先されるのでしょうか?
どちらが先に作成されたか?を場合分けして、具体例で解説します。
子:B、C、D
(1)遺言 → 家族信託
まず、父Aは「すべての財産を子Cに相続させる」という内容の遺言を作成しました。
その後、父Aが子Bとの間で信託契約を締結し、その契約の中で「父Aが死亡して信託が終了した後、財産は子Bに承継させる」と定めました。
この場合、家族信託が優先されます。遺言は信託契約の作成後も、撤回・書き換えが可能だという特徴があるからです。
遺言作成後に家族信託が契約された場合は、財産の信託化により管理が受託者へ移りますので、信託の契約により自動的に遺言が撤回されたものとして扱われます(民法第1023条・1024条)。
(2)家族信託 → 遺言
まず、父Aと子Bが、父Aが死亡して信託が終了した際には、子Bが信託財産をすべて承継するという内容の信託契約を締結しました。
その後、父Aは「すべての財産を子Dに相続させる」という内容の遺言を作成したと仮定します。
この場合も家族信託が優先されます。
なぜなら、父Aが子Bに対して信託をすると、財産は子Bに譲渡されたことになり、父の固有財産ではなくなるからです。
税法上、受益権はみなし相続財産として相続税の課税対象ですが、受益権は相続法上の相続財産には該当しません。
父Aが信託された財産について遺言を書いたとしても、その財産はすでに信託財産となっていますので信託契約が優先されることになります。
いずれの場合も、家族信託の方が優先される
以上のように、どちらの順番であっても家族信託が優先されるという結果になりますが、ここで押さえておきたいポイントがあります。
「相続性のある受益権」は遺言の対象となる点と、家族信託を撤回することによって、遺言を有効にすることができるという点です。
[1]「相続性のある受益権」は遺言の対象になる
信託をすると、受益者である父Aには受益権が発生します。
受益権は売買・贈与も可能なため、この受益権を対象として遺言を作成することは可能です。
ただし受益権には信託契約の内容によって「相続性のある受益権」と「相続性のない受益権」に分けられ、遺言の対象とできるのは「相続性のある受益権」のみになります。
(2)の場合において、受益権は父Aの死亡により信託が終了し、子Bの承継が指定されているため、相続性については「相続性のない受益権」に該当します。
そのため(2)のケースでは遺言の作成はできない事になります。このように信託契約により違いが生じる点に注意しましょう。
信託の組成については専門知識が必要なケースが多いため、とくに二次相続まで検討している際は専門家へぜひご相談ください。
[2]家族信託を「撤回」することで遺言を有効化できる
重要なポイントの2つ目として、(2)の場合、家族信託を撤回することで遺言の方を有効にすることができるという点です。
信託法では、原則として委託者兼受益者によって信託契約を一方的に解除できるからです。
[3]家族信託の撤回を避けるには「撤回不能型信託」を作る
しかし、受託者としては信託契約を一方的に解除されるのを避けたいケースもあるでしょう。
このような事態を避けるため、【撤回不能型信託】を作ることができます。
信託契約に
「一方的に契約解除できない」
「受託者を解任できない」
「信託契約の内容を変更できない」
こういった内容を緻密に盛り込んでいくことで撤回不能な信託を組成でき、信託契約で定めた財産の承継内容を確実に実現できるようになります。
遺言には撤回を防ぐ方法はありませんので、ここでも家族信託が有利に働くことになるといえるでしょう。
それぞれの特徴及び、信託ではできて遺言ではできない部分(撤回の可否の選択)などは相続のサポートをするうえで重要な知識となるので、ぜひ押さえておいてください。
まとめ
家族信託には遺言的な機能もありますが、家族信託と相反する内容の遺言が作成された場合には、家族信託のほうが優先されます。
その際、「相続性のある受益権」は遺言の対象になること、家族信託を撤回することで遺言を有効にすることができるという2つのポイントを、ぜひ押さえておいてください。
また、我が家に家族信託は必要ないのではないか、遺言だけで充分ではないかというご意見もあるかと思います。
家族信託の必要・不要の判断基準についてはこちらの記事『自分には家族信託は必要ない?必要・不要の判断基準を解説!』で解説しています。
家族信託は、決してお金持ちや不動産持ちの人だけのものでもありません。持っているのは預貯金のみ、という場合でも信託契約は意外に有効で、活用度の高い方法となります。
契約には委託者の意思能力が必須ですので、高齢になる親のサポートに不安を感じている場合など、家族信託についての検討をお勧めします。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する