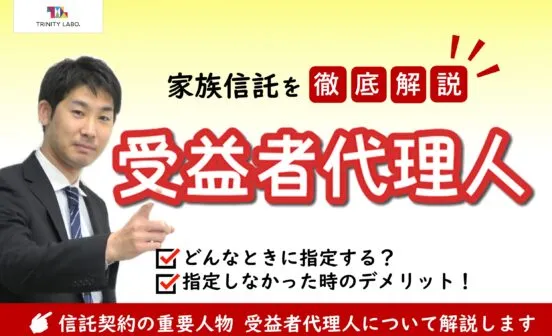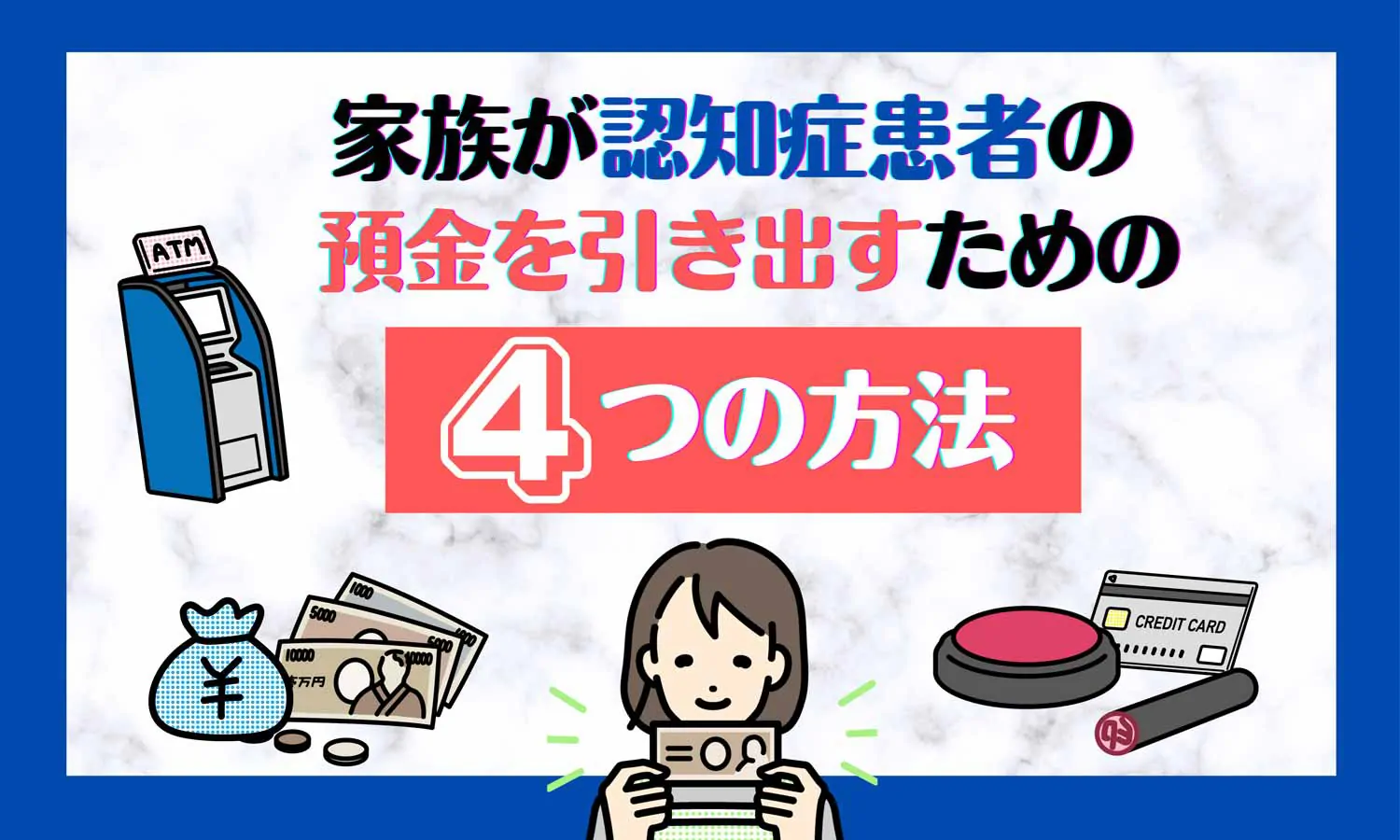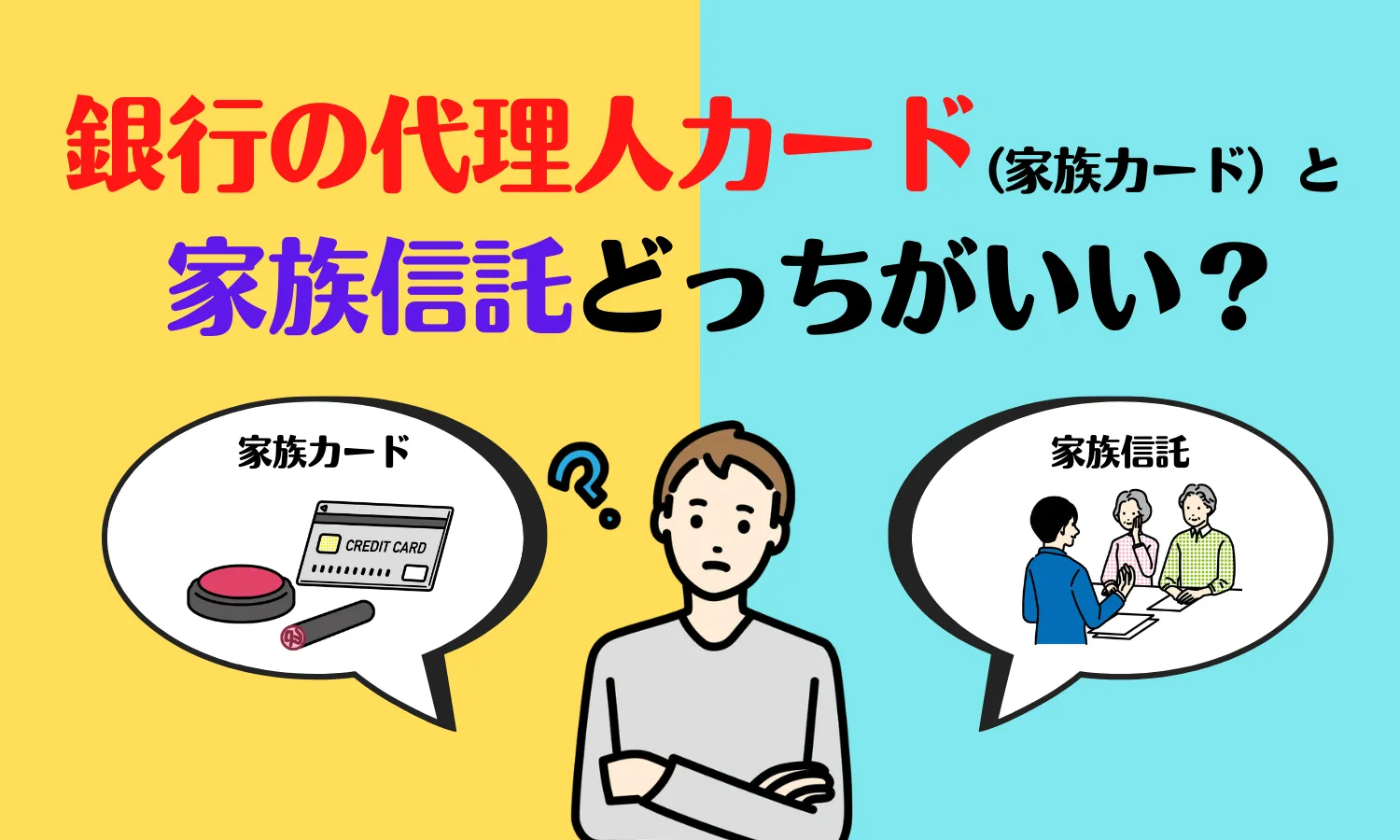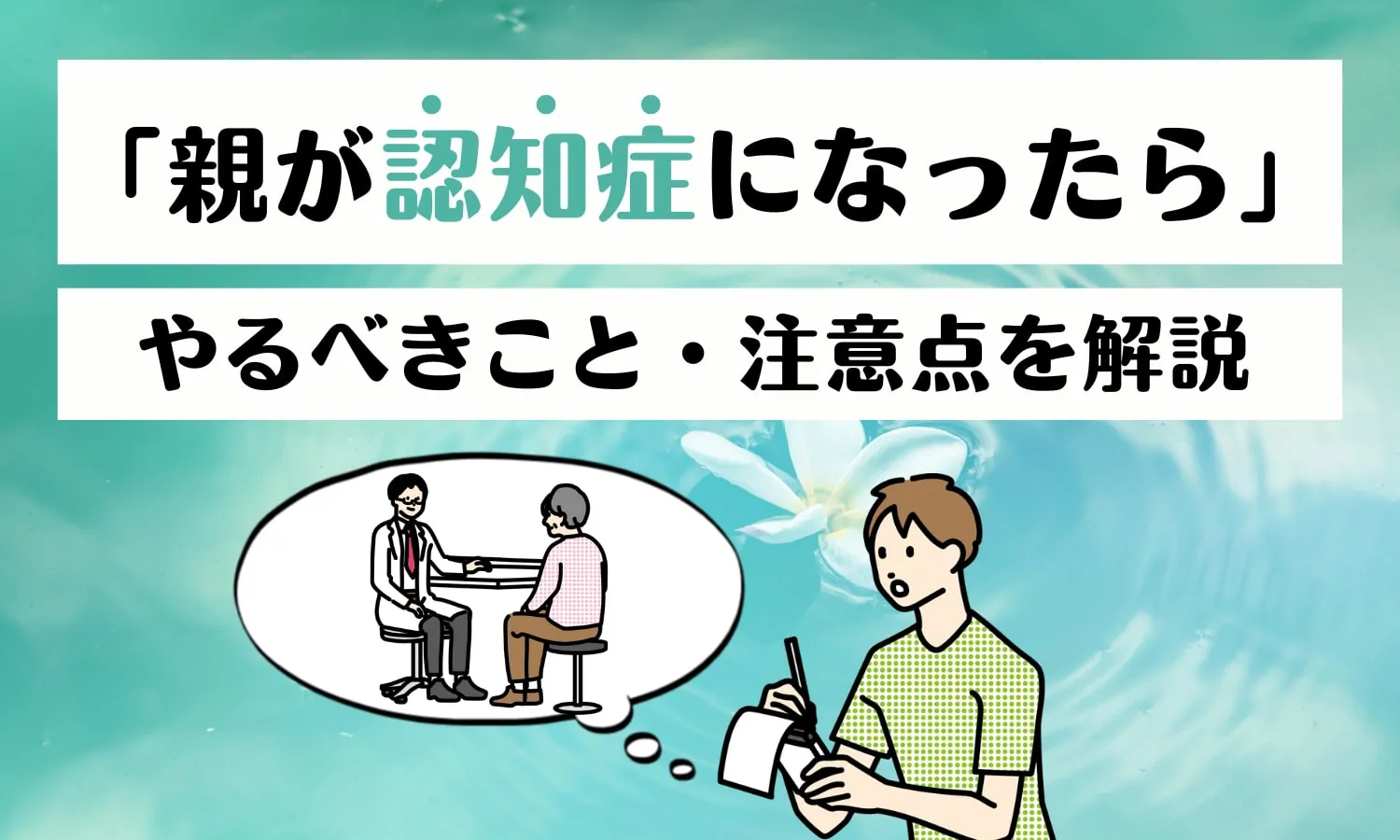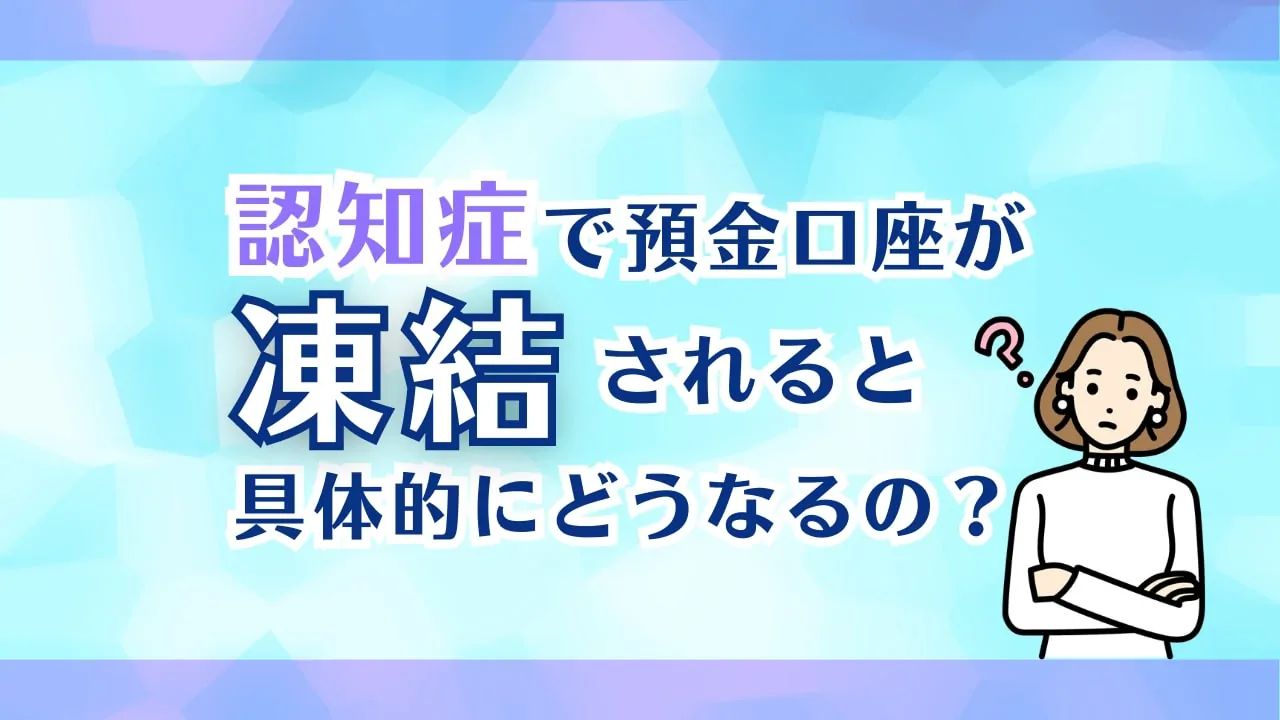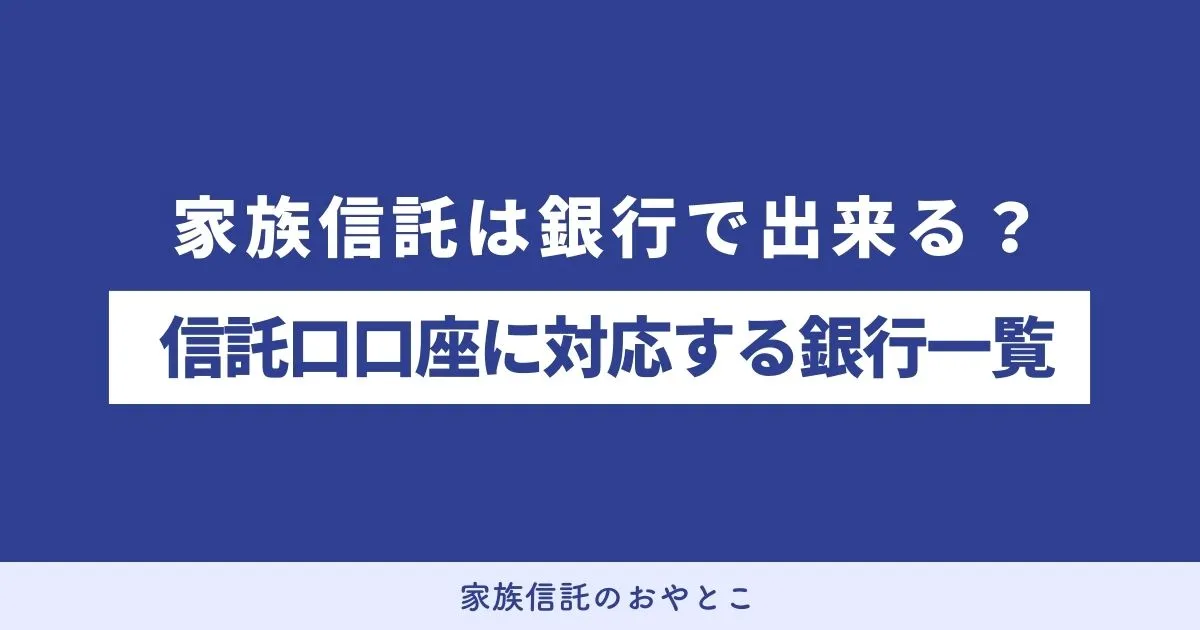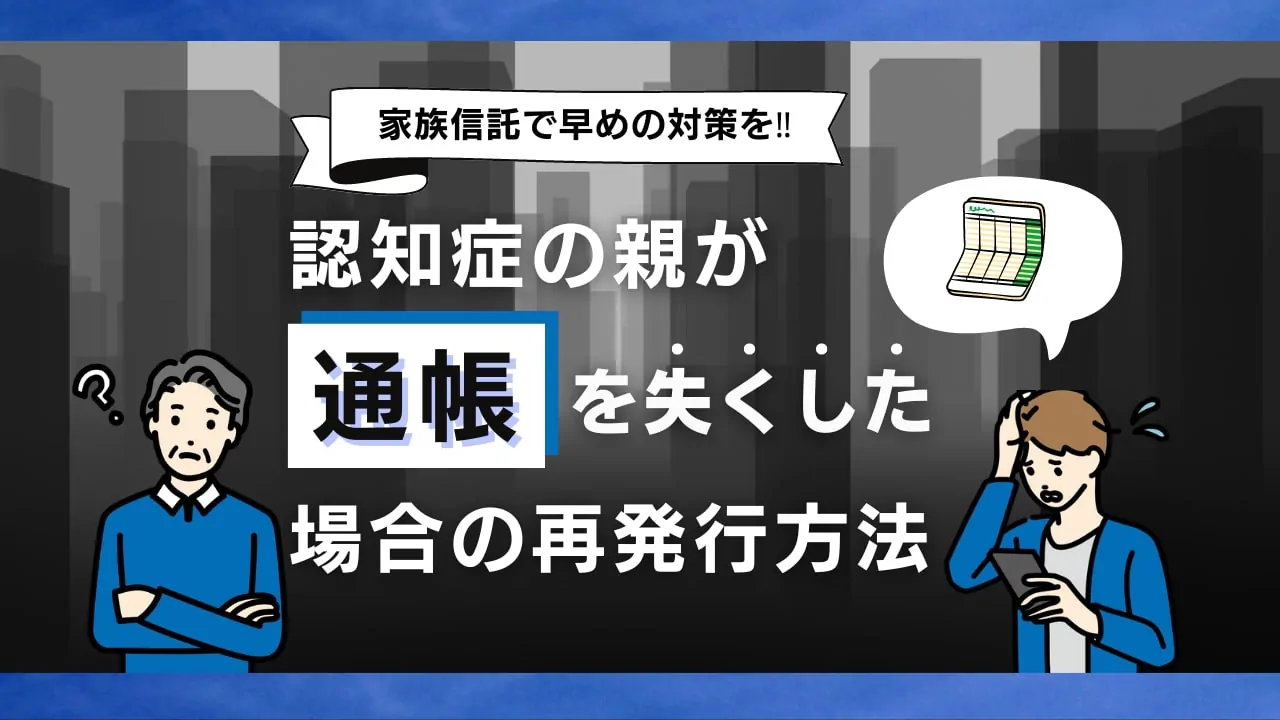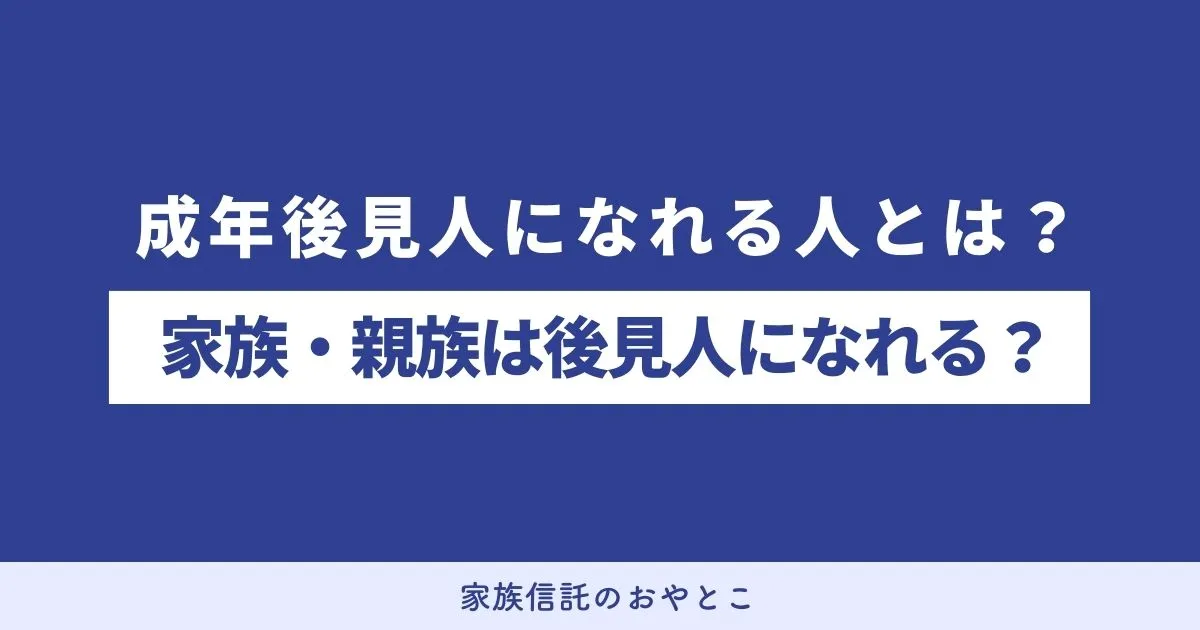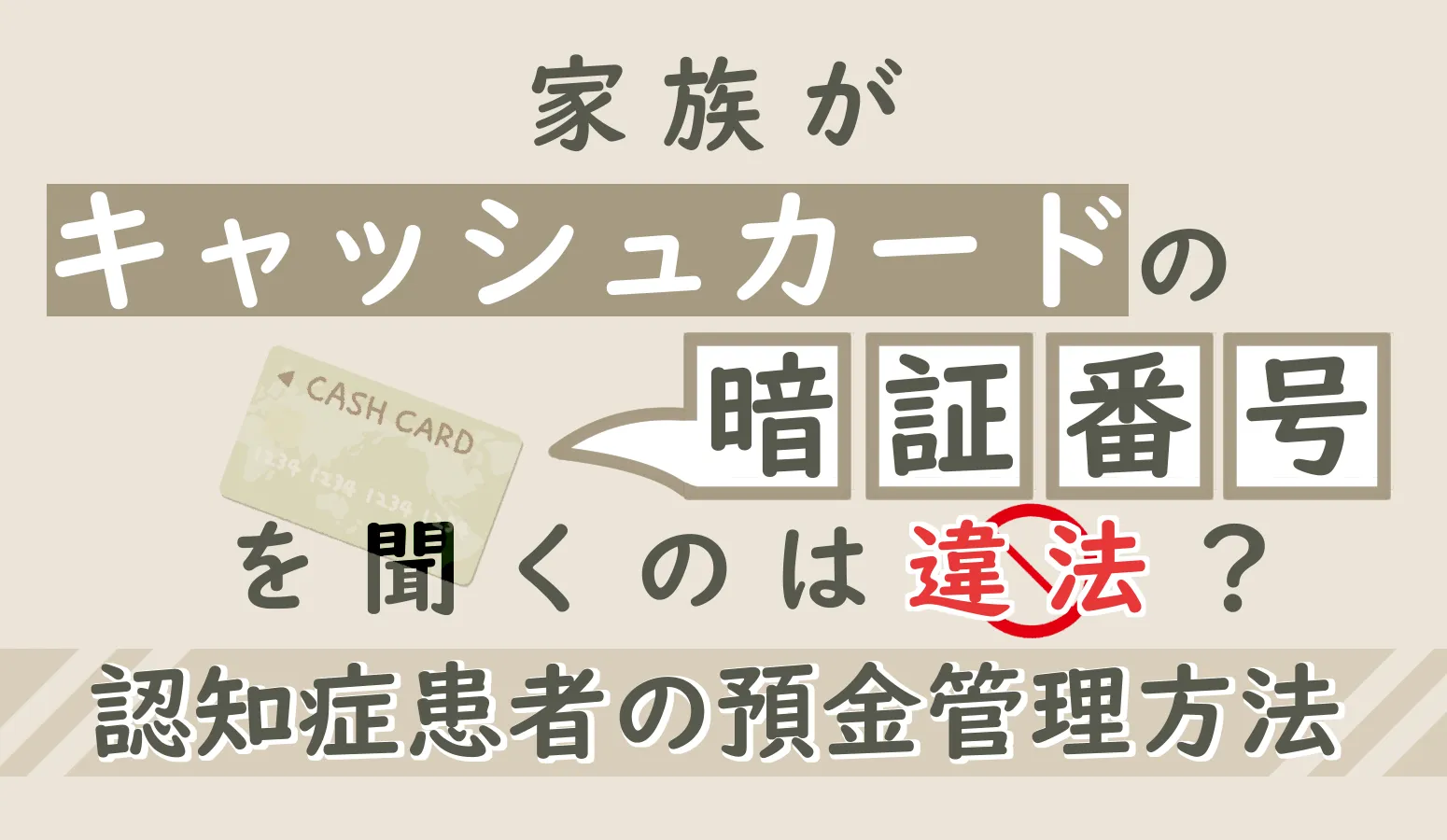(後半動画はこちら)
家族信託の契約で受益者の代理人である『受益者代理人』
を選任、指定できることをご存知でしょうか?
受益者の判断能力について不安がある、あるいは問題が生じるといった場合、受益者代理人を置くことで、受益者の代わりとなり、権限を行使する形にすることができます。
今回は受託者代理人を置く理由や、選任・指定に関する注意点について解説します。
※家族信託の契約や利用の流れについてはこちらの記事でも解説しています。
家族信託とは?わかりやすくメリット・デメリットを徹底解説します
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度です。認知症が進行し意思能力を喪失したと判断されてしまうと、銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)、自宅を売却できないなどのいわゆる「資産凍結」状態に陥ってしまいます。そのような事態を防ぐために、近年「家族信託」が注目されてきています。この記事では家族信託の仕組みやメリット、デメリットをわかりやすく解説します。
要約
- 受益者代理人とは、文字通り「受益者」を「代理する」人物
- 受益者は利益を受け取るだけでなく契約の内容の変更など判断能力が必要
- 受益者の判断能力が低下した際、家族信託の契約に支障をきたすことがある
- 「受益者代理人」がいることで権利の行使が可能になり、もしもの時の備えに
- ただし、あらかじめ信託契約書に「受益者代理人を選任、指定する」旨の記載が必要
- 受益者に判断能力のあるうちは「受益者代理人」を指定しない
- 未成年者や家族信託における受託社は「受益者代理人」になることができない
- 受益者の判断能力について不安がある場合、まずは専門家へ相談を
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する
目次
受益者代理人とは
受益者代理人とは、文字通り「受益者」を「代理する者」です。
信託法上は、「代理する受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者」と規定されています。
家族信託では一般的に「委託者=受益者」(いわゆる自益信託)で契約をスタートさせるため、受益者というと委託者を指すケースが多くなります。
これは信託財産から得る利益を委託者(信託財産の元々の所有者)以外の人が得ると贈与税が課税される可能性があるからです。
しかし、中には「受益者=委託者」ではないケースもあります。受益者が複数いる場合もあるからです。
受益者には判断を必要とする役割がある
このような受益者を代理する人が必要になるケースとは、どのような状況なのでしょうか。
受益者の代理人が必要になる理由として、受益者が単に信託から利益を受け取るだけではなく、信託法上、判断を必要とする役割もある ことが理由となります。
- 信託契約の内容の変更
- 受託者の辞任、解任
- 合意によって信託を終了させる
これらは信託の根幹を成すものであり、このような大事な場面においては受益者の判断能力が必要となり、信託の運営にも大きくかかわってきます。
そのため、受益者代理人を選任して受益者に代わって同意したり、合意したりという必要性があるのです。
受益者に代理人が必要となる状況について
実務上ではどのようなケースにおいて受益者代理人を選任・指定をするのでしょうか。例として以下のような内容があります。
- 受益者が認知症や後見開始になった場合
- 受益者が未成年や高齢者の場合
受益者の判断能力について不安がある、あるいは問題が生じる可能性があるため、受益者の判断能力が低下した時に権限を行使できるように 備えておく必要があります。
また、家族信託では幼い子どもも受益者とすることが可能であるため(こちらの記事で解説しています)、判断が必要な時に備えて受益者の代理人を置けるように備えることができます。
【注意点】受益者代理人の設置には選任、指定できる旨の定めが必要
信託契約において受益者代理人を指定する場合は、信託契約書を作成する際に、受益者代理人を選任、指定する旨をあらかじめ定めておく 必要があります。
信託契約の中に「受益者代理人を定めることができる」と定めておくことで、初めて裁判所が選任することができます。
信託契約で「受益者代理人を定めることができる」という記載がなければ、いざ受益者代理人を選任したいと思った時でも選任することができないのです。
この点が、受益代理人の設置についての注意点であり、信託監督人(受託者を監督する役目)と異なる点でもあります。
したがって、信託契約書を作成するときには必ず、この受益者代理人の選任の規定を入れておくようにしてください。
将来的に受益者代理人が必要になるかどうか、実際に指定するかどうかは個々のケースによりますが、あらかじめ信託契約書に規定を入れておかないと指定そのものができない という点に注意しましょう。
【注意点】受益者の判断能力があるうちは受益者代理人を指定しない
受益者の判断能力が低下する見通しになると、受益代理人の指定が必要なタイミングが近づいているといえます。
受益者の代わりに判断の役割を担う受益者代理人ですが、指定するタイミングの注意点として、受益者に判断能力のあるうちは受益者代理人を指定しない方が良い
という点があります。
一度、受益者代理人が指定されると、信託法に定められている一定の権利を除き、受益者の権利行使が制限されることになるからです。
受益者代理人を置いた以上はその人に任せなければならず、受益者自身が判断を行使したくても、それが不可能となります。
そのため、受益者の判断能力に問題が無いうちは受益者が自ら権利行使できるように、受益者代理人は指定しないほうが良いといえるでしょう。
このような点が受益者代理人を指定する際の注意点だと言えます。
受益者代理人になれない方
最後に、受益者の代理人になれない例を説明します。
2. この信託における受託者
1の未成年者は法的にも判断能力が不十分だという理由によります。
2は、そもそも受益者というのは受託者を監督するという立場にあるため、監督する側と監督される側が同じであれば、監督機能が働かないことになるからという理由によります。
受託者を監督する際の対策については、こちらの記事で解説しています。
まとめ
受益者代理人を選任・指定する際のポイントとして以下の2つがあります。
POINT2 受益者の判断能力があるうちは、具体的に受益者代理人を指定しないこと
受益者についてこのような制度があるという点を、ぜひ知っておくとよいでしょう。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する