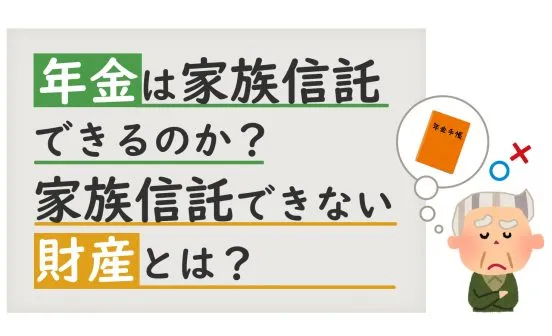自分の財産の一部を頼れる家族に託して管理してもらう「家族信託」ですが、中には信託できない財産も存在します。
家族信託ができない財産にはどのようなものがあるのでしょうか?
老後生活で重要な収入源となる年金はどうでしょうか?
本記事では、年金を家族信託したい場合の対処法や具体的な手続きについて、わかりやすく解説していきます。
家族信託の仕組みについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する
目次
親の「年金受給権」を信託することは可能?
家族信託では信託したい財産を話し合い、信託契約で定めることができます。
預貯金を信託する場合は、家族信託専用の銀行口座(信託口口座)を作成し、信託する分の金額を信託口口座へ移行します。
既存の定期預金や普通預金に入っているまとまった額の金銭はこの手続きで移せますが、公的年金は今後も委託者(親)個人の口座に偶数月に振り込まれます。
この年金についてはどうしたらよいのでしょうか。
年金受給権とは?
年金は、個人が「年金受給権」という権利を有することで受給できます。
年金受給権は、その権利を持つ本人のみに帰属する「一身専属権」です。
一身専属権は本人以外に譲渡できないもので、他にも「生活保護受給権」や「使用借主権」などがあります。
また「親権者としての地位」なども一身専属権に含まれるものとされています。
国民年金法24条や厚生年金保険法41条などにおいて、年金受給権の譲渡は禁じられています。
厚生年金保険法
(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
国民年金法
(受給権の保護)
第二十四条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
そのため、年金の振込口座には受給権を持つ本人の口座を指定する必要があります。
家族信託で使用する信託口口座は「受託者名義」であり、年金を受ける本人名義ではないため、年金の受給口座に指定することはできません。
ただし、本人の口座に振り込まれた年金を「金銭」として信託財産に含めることはできます。
では、振り込まれた後の年金を活用(信託)するにはどうすればよいのでしょうか。
振り込まれた年金を活用(信託)する方法
信託口口座を年金の振込先に指定できないのであれば、年金が唯一の収入源になっている場合などは、どう対処すればよいのでしょうか。
この場合、年金が本人の口座に振り込まれた後、その預金残高を信託口口座へ移すことは可能です。
家族信託の対象にできないのは「年金受給権」のみであるためです。
支給される年金を委託者のために活用(信託)するための具体的な方法をみていきましょう。
1.委託者の意思能力がある時期
委託者が元気なうちは、年金を受給するたびにそれを信託財産に加えることが可能です。
追加で信託財産に入れる契約手続きをして、委託者が個人口座から信託口口座に振り込み、資金移動をします。
ただし委託者の個人口座から払い出し手続きを要するため、委託者の意思能力が必須となります。
2.委託者の意思能力を喪失した後
委託者本人が意思能力を喪失した後は、上記1.の手続きはできなくなるとともに、新たな信託契約も不可能となります。
そこで、実務上は、信託財産とせずに、年金を固定費の引き落とし資金とする方法があります。
年金の受給口座を、本人の生活に係る水道光熱費や介護費用、税金、住宅費などの固定費引き落とし口座とするのです。
つまり、振り込まれた年金が自動的に本人の生活費の一部として利用されていくルートを作っておきます。
こうすることで、実質的に年金を自動的に生活資金へ充てることができます。
実務上信託が難しい金融商品での対処方法
年金受給権のように「法律上信託できない」というわけではなくとも、実務上手続きが難しい財産もあります。
その代表例が、有価証券や有価証券(投資信託や上場株式など)です。
有価証券を信託する場合、家族信託に対応する証券会社の「信託口口座」に移管し、運用していく必要があります。
しかし、証券会社や商品によっては、家族信託に対応していないケースもあるため、事前に確認が必要です。
証券会社での手続きについては、以下の記事でより詳しく解説しています。
株式や投資信託を家族信託する〜証券会社で必要な手続きを解説
家族信託を計画しているとき、株式や投資信託などを信託財産にしたいと思っている方も多いのではないでしょうか。その場合には証券会社での手続きが必要となりますが、どのような手順が必要なのでしょう。この記事では、上場株式や投資信託などといった金融商品を家族信託する場合の証券会社での手続きや注意点などについて解説します。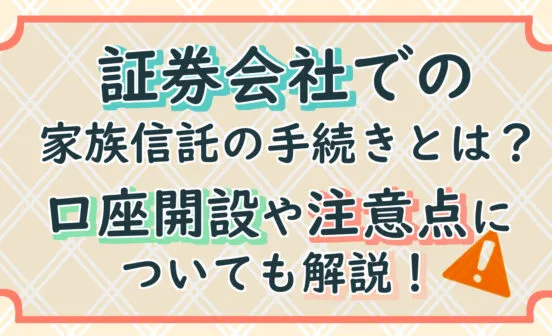
1.現在利用中の証券会社が信託に対応している場合
まずは、現在その金融商品を保有している証券会社が家族信託に対応しているかどうかを確認しましょう。
信託に対応している証券会社の代表例としては、野村證券、大和証券、楽天証券などがあります。
保有商品をそのまま信託口口座に移せるのであれば、口座間で移管します。
2.他の証券会社に信託口口座を作って移管する場合
家族信託に対応している他の証券会社に信託口口座を作って移管する場合、移管先が現在保有中の金融商品に対応しているかどうかがポイントとなります。
証券会社によって信託口口座に対応している商品の種類が限られている可能性もあるからです。
3.移管や信託口口座の作成が難しい場合の対処法
もし移管ができない等、信託が難しい場合は信託財産から除外する、解約して現預金として保有するなどの方法があります。
移管や信託口口座の作成が難しい場合の対処法
- 信託財産から除外して現状のまま保有する
- 解約をして金銭として銀行の信託口口座に移す
- 解約資金をもとに信託口口座のある証券会社にて新規で有価証券等を購入する
有価証券等の取扱いについては課税面での注意点が多く、証券会社での信託口口座開設には一定の規程もあります。
現在のまま保有する場合は、保有者(委託者)の意思能力の低下により運用が難しくなる可能性もあります。
そのため、金融商品の現在価額や保有量によっては、他の信託財産や損益などを総合的に考慮し、解約を検討することもあります。
判断には専門的な知識が必要となりますので、信託を検討する際は家族信託の専門家に相談するのがおすすめです。
その他、信託の際に注意が必要な財産は?
金融商品の他にも、信託を検討する際に注意を要する資産や事柄があります。
例えば、ローンが残っている不動産は信託できるのでしょうか。
契約上の「信託」はできたとしても、実際に財産管理・運用をしていくなかで受託者が行えない行為はあるのでしょうか。
これらの注意点については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。
家族信託にデメリットはある?後悔しないための15の注意点!
家族信託にはデメリットが存在します。しかし、デメリットをしっかり理解したうえで組成することで、リスク回避が可能です。本記事では、家族信託のデメリットや注意点、デメリットを考慮しても家族信託がおすすめのケースなどについて詳しく解説します。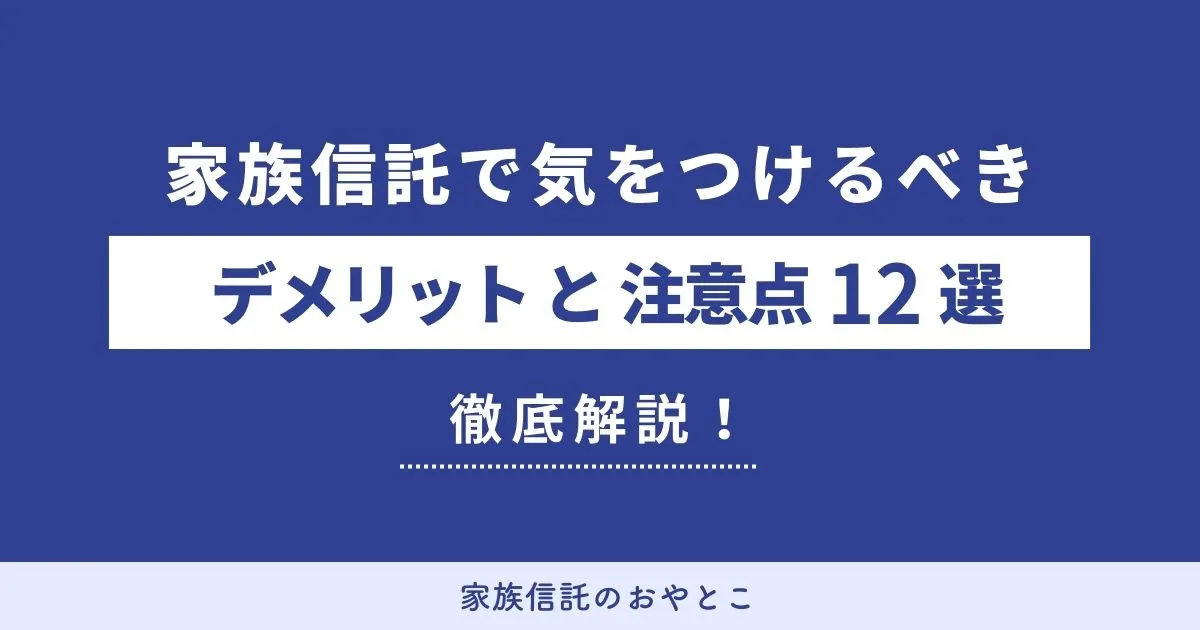
まとめ
年金受給権など、家族信託ができない資産について解説しました。
法律により信託ができない規程でも、介護費用・老後費用として活用できる方法があることが分かりました。
また、実務的に信託の難しい資産については、事案ごとに慎重な検討が必要となります。
シンプルに考えるのであれば、家族信託しやすい資産を除外して、まずは急いで備えるべき介護費用等の準備に取り掛かる、という取捨選択をする方法もあるでしょう。
信託契約は家族ごとに優先順位があるでしょうし、契約の緊急度も異なると思います。全体を見渡して検討していきましょう。
うまくいかない場合や対応方法が難しい場合は、ぜひ経験豊富な専門家に相談をしてみてください。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する