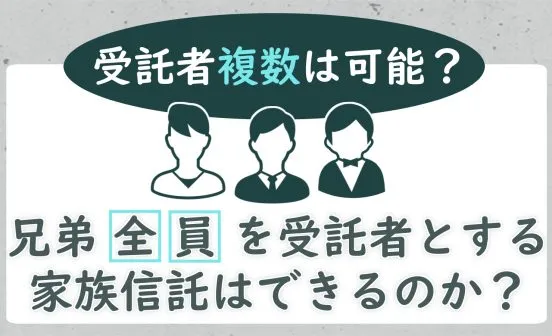家族信託では「誰が受託者になるのか」について兄弟間で議論になることもあるかもしれません。
適任者がいても「仕事が多忙である」「遠方に居住している」「責任の重い役割を1人で引き受けたくない」など様々な事情があるでしょう。
そこで「受託者を複数人にできますか?」というご質問をよくいただきますが、結論からいえば可能です。
信託法上、受託者の人数に制限はありません。
ただし、受託者を複数にすることには、デメリットや注意点もあります。
そこで本記事では、受託者を複数にするメリットとデメリット、そしてデメリットを回避するための家族信託の設計方法についても詳しく解説していきます。
家族信託の仕組みや基礎知識については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
目次
受託者の負担は大きい?
受託者は委託者から信託契約で託された財産の管理・運用を行います。
信託契約である以上、家族信託の受託者には「善管注意義務」「忠実義務」「公平義務」「分別管理義務」など、信託法上の様々な義務が課せられます。
託された信託財産や信託についての事務に注意を払いつつ、信託の目的に沿って誠実に財産を管理していかなければなりません。
受託者の義務や仕事については以下の記事でも詳しく解説しています。
【家族信託の報告義務】家族信託をしたら受託者は面倒な作業が必要?
高齢になった親のサポート目的などで成年後見制度を利用した場合、親族が後見人に就任すると、毎年、家庭裁判所に収支状況等の報告義務があります。「財産目録」や「収支状況」等の内容です。では、家族信託を利用した場合、そのような報告義務はあるのでしょうか。受託者が作成する義務のある書類の内容について見ていきましょう。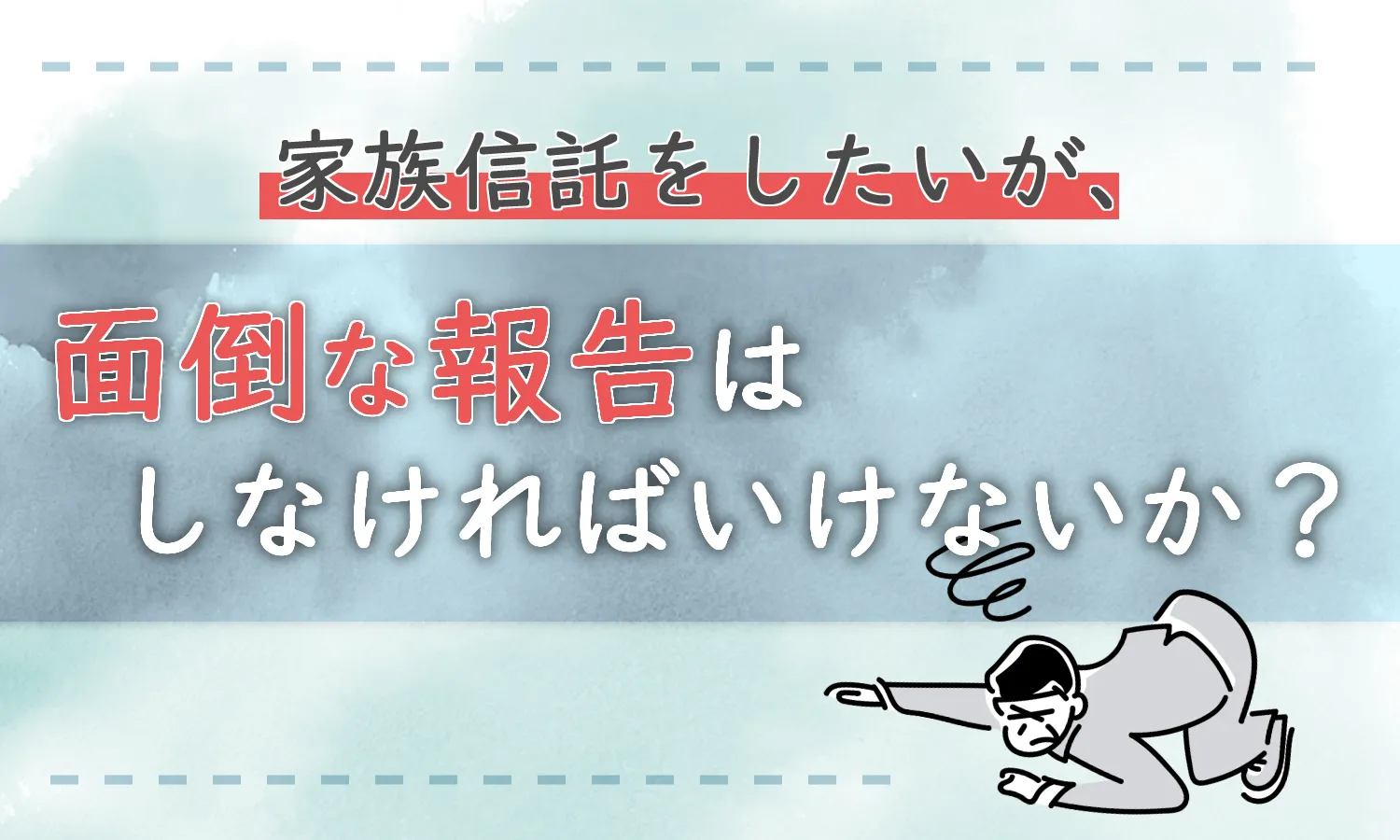
実際に受託者の負担が大きいかどうかは、信託財産の内容や額、契約内容によっても異なります。
負担が大きいと感じる場合は、受託者を2人以上とすることも1つの選択肢です。
ただし、メリットもあればデメリットもありますので、以降で解説していきます。
家族信託について知りたい方へ

親御様が認知症になり判断能力がなくなると、本人の預金が引き出せないなどの「資産凍結」
が起こる可能性があります。
「家族信託」では、元気なうちに財産を家族に託しておくことで、資産凍結を防ぎ、柔軟な財産管理が実現します。
ただし「受託者(主に子)」には、法律で定められた義務(信託財産に関する記録や報告など)もありますので、理解しておく必要があります。
家族信託の契約数No.1*のおやとこでは、経験豊富な専門家が真心をこめて丁寧に対応いたします。
「相談だけ」でも大丈夫。まずはお気軽にお問い合わせor資料請求いただければ幸いです。
 無料で相談する
無料で相談する
*2023年11月期調査(同年10月15日~11月11日実施)に続き3年連続
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
受託者を複数人にするメリット
受託者を複数人にするメリットとしては、以下が挙げられます。
受託者を複数人にするメリット
- 受託者の負担が分散する
- 不正や不備がないように受託者同士で監督し合える
- 判断に迷ったときに受託者同士で相談できる
受託者が複数人であれば、信託財産の管理がおろそかになったり、私的に利用したりという問題の回避にもつながります。
また、信託の事務に関する判断に迷ったとき、受託者同士で相談できれば、一人に過度な負担がかかるということも防げ、慎重かつ合理的な意思決定も可能となります。
信託法が複数人の受託者を許容しているのは、上記のようなメリットがあるからともいえます。
「誰が受託者になれるのか」については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
家族信託の受託者の役割・義務とは?誰がなるべき?選び方のポイント
今回は、家族信託で財産を預かる「受託者」について解説します。誰が受託者になれるのかという点は、家族信託のご相談の中で、よくいただくご質問です。その中でも、今回は、「未成年者・家族(子、孫などの直系親族)以外・複数名・委託者・受益者」これら5つの立場・状況にある方が、家族信託の受託者になりうるか、解説していきます。また受託者になった後にしなければならないことも解説します。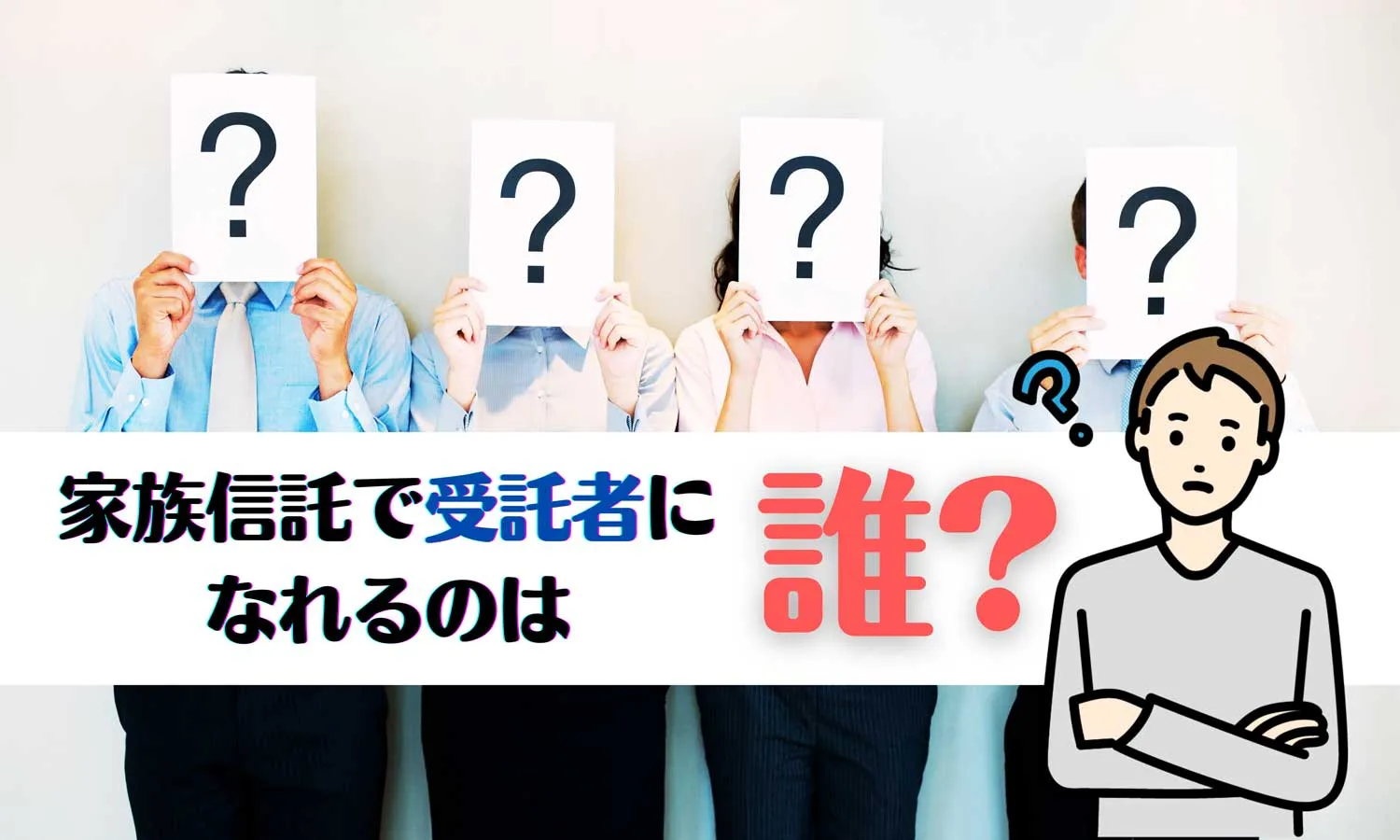
受託者を複数人にするデメリット
一方で、受託者を複数にした場合は、以下のようなデメリットも考えられます。
受託者を複数人にするデメリット
- 信託の運営が停止するおそれがある
- 信託内で決定した債務は受託者間の連帯債務となる
それぞれみていきましょう。
デメリット1.信託の運営が停止するおそれがある
原則として信託事務の処理は 「受託者の過半数」で決するとされています(信託法第80条)。
受託者の意思決定については、信託契約内で別段の定めや事務の分掌に関する定めを設けることも可能です。
一方で、複数の受託者の意見が合わず、信託が進められなくなる(信託の運営が停止する) おそれもあるため、注意が必要です。
デメリット2.信託内で決定した債務は受託者間の連帯債務となる
受託者が信託事務を処理する際に、各受託者が第三者に対して負担した債務は連帯債務となります。
頻繁に発生する内容ではないかもしれませんが、たとえば、信託財産(不動産)を担保に入れて信託内での借入をしたケースなどが該当します。
これは信託上の業務としての借入であり、本来は個人で借りた債務ではありません。
しかし、信託業務の責任をもつ者として、その債務を共同で負うことになるのです。
仮に債権者から債務の弁済を求められた場合には、受託者として全員が連帯して負担することになります。
よって、相互の意思疎通や連携が求められるため、受託者としての責任を自覚した上で業務を行うことが重要です。
受託者を複数人にせず信託組成を工夫する方法
受託者を複数人にするデメリットを回避するためには、以下のように信託の組成を工夫する方法があります。
受託者を複数人にせず信託組成を工夫する方法
- 複数人ではなく「第二受託者」を設定する
- 監督役として「信託監督人」や「受益者代理人」を設定する
- 信託契約を複数契約する
上述のとおり、受託者を複数にすることは可能ですが、信託が進められなくなるリスクも考えなければなりません。
信託財産の額が大きく、その運用に重要かつ迅速な意思決定が求められる場合はとくに、受託者を複数人とするデメリットを十分理解しておく必要があります。
また、そのデメリットを回避するために、受託者を複数人とせず、信託の組成を工夫する方法がありますので、解説していきます。
方法1.複数人ではなく「第二受託者」を設定する
受託者を複数にするのではなく、例えば「第一受託者」である長男がなんらかの理由で受託者として信託事務を遂行できなくなった場合に備えて、あらかじめ次男を「第二受託者」として定めておくことができます。
「もしもの時に備える」という意味合いのため、長男と次男は完全に対等な立場ではありませんが「兄弟ともに信託に関わる役割を持つ」という設計によって、負担の分散が期待できます。
方法2.監督役として信託監督人や受益者代理人を設定する
本来は受託者の監督役になりますが「信託監督人」や「受益者代理人」として兄弟を設定する方法もあります。
例えば、受託者には次男が就任し、長男を信託監督人や受益者代理人などとして、次男の信託事務を監督するという形です。
「信託監督人」「受益者代理人」を定める場合は、信託契約内でその旨を記載します。
信託監督人は受託者の財産管理などを監督し、受益者代理人はもともと受益者が有する管理者的な役割(信託契約の変更や受託者の解任等)を代理します。
これらの役職に兄弟が就くことで、受託者の監督だけでなく相談役としての協力も可能となります。
信託監督人の役割については、以下の記事で詳しく解説しています。
信託監督人とは?〜家族信託を監視・監督する重要な役割〜
この記事では「家族信託の重要人物〜信託監督人〜」と題して、家族信託における「信託監督人」についてお伝え致します。家族信託では委託者は資産の管理・運用を受託者に依頼しますが、さまざまな理由から、受託者の財産管理に不安があるケースもあると思います。その場合に活用できる信託監督人について、この記事でご紹介します。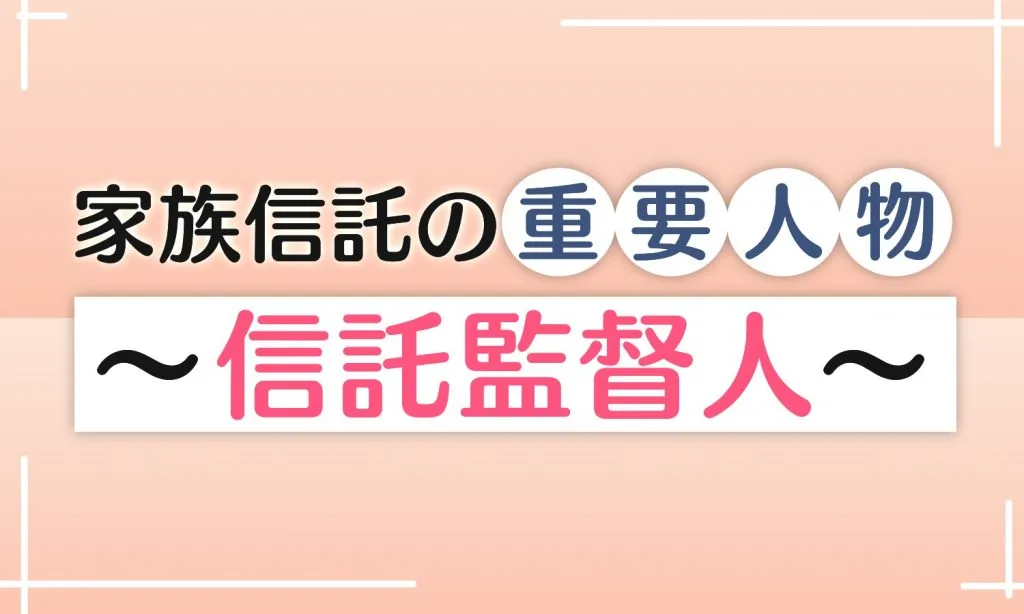
方法3.信託契約を複数作成する
委託者が同じで受託者が異なる複数の信託契約を締結するという方法もあります。
具体的には、兄弟ごとに信託で管理する財産を分け、それぞれを受託者として設定するという形です。
例えば、委託者が信託したい財産として、不動産A、不動産B、現金5000万円があったとします。
長男と次男に信託を依頼し、長男とは不動産Aと現金2500万円の信託契約を、次男とは不動産Bと現金2500万円の信託契約を締結します。
このように分割することで受託者を複数人にはせず、公平に兄弟間で受託者の業務を分担できます。
ただし、複数の不動産を別の信託として分けた場合、それぞれの不動産の間では損益通算ができないリスクが生じる可能性もあります。
契約内容の設計には専門知識が必要となりますので、ご検討の際は家族信託の専門家にご相談ください。
まとめ
以上のとおり、受託者の負担が気になる場合は、メリット・デメリットを踏まえて、各事情や受託者間の関係性を踏まえた検討をお勧めします。
受託者を複数にする方がシンプルのように感じますが、大型の資産を有している場合については、受託者が複数人になったときのデメリットを押さえて信託組成を工夫していきましょう。
また、信託契約を複数作成した場合でも、兄弟はお互いに監督役(信託監督人)に設定すれば、信託事務についての相談や協力が可能です。
家族信託の受託者について疑問や不安をお持ちの方へ

家族信託の受託者に兄弟で就任することで、お互いの負担が軽減するなどのメリットがあります。
ただし、信託の運営には受託者の合議が必要です。
場合によっては、合意が得られずに信託の運営が停止するリスクもあります。
受託者の負担を軽減しつつ、このリスクを回避するには、信託契約自体を複数作成したり、その他の役割を活用したりと、ケースに応じた対策が必要です。
信託の設計には法律や税務など、専門的な知識が必要となりますので、まずは専門家にご相談ください。
お問い合わせ実績20,000件を超える家族信託の「おやとこ」では、経験と知識が豊富な専門家が真心をこめて対応いたします(相談は無料)。
 無料で相談する
無料で相談する