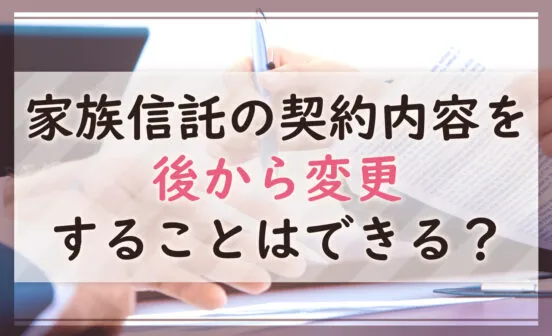適切な手続きを踏めば、家族信託の契約内容を後から変更することは可能です。
家族信託は一般的に何年もの間続くため、当初の契約内容を変更する必要が生じるケースもあります。
契約期間中に不測の事態が生じたり、当初の考えと変わったりする可能性があるためです。
ただし、契約変更には一定の注意が必要です。
そこで本記事では、信託契約の変更手続きや、知っておくべき注意点を詳しく解説していきます。
家族信託の仕組みや基礎知識については、以下の記事で詳しく解説しています。
家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する
目次
信託契約後に契約内容の変更が必要となるケースとは?
信託契約後に契約内容の変更が必要となるのは、具体的にどのようなケースが考えられるでしょうか。
2つの事例をみていきましょう。
ケース1.受益権の承継者や承継する割合を変更したい
信託契約を開始してから承継者等の変更をしたいケースが考えられます。
家族信託では、当初の受益者(主に親)に帰属していた受益権の承継について定めることができます。
受益権を承継する人、複数人で承継する場合はその割合、そして遺言では指定できない複数世代に渡る承継まで、細かく定めることが可能です。
その内容を当初の契約から変更したい場合は、信託契約を変更する必要があります。
具体例は以下のようなケースです。
● 当初の信託契約では父の受益権を長男が承継するとしていたが、意向が変わり、受益権の承継者を次男に変更したくなった。
● 当初の信託契約では、父の受益権を長男、次男、三男がそれぞれ3分の1の割合で承継するとしていた。しかし、その後長男が死亡したため、次男に2分の1、三男に2分の1の割合で受益権を承継させるように変更が必要となった。
ケース2.信託不動産の管理や処分の方針に変更が生じた
親御様が認知症などで判断能力をなくし、不動産の売却や運用ができなくなることに備えて、不動産を家族信託するケースは多くあります。
不動産の売却や賃貸、工事の契約など、当初の信託契約において定めていなかった権限を受託者へ与えたい場合は、その旨を追加しなければなりません。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
● 当初の信託契約では不動産を売却する予定がなかったため、信託契約で「受託者が不動産を売却できる」旨を定めていなかった。しかし急遽不動産を売却しなければならない事情が生じたため、信託契約書に「受託者が不動産を売却できる」旨を追加する必要が生じた。
● 賃貸する予定がなかった自宅不動産について、事情が変わり、賃貸することとなったが、信託契約書内で自宅不動産を賃貸できる旨を定めていなかったため、その旨を追加する必要が生じた。
信託の変更を見据えて最初の段階から対策することも可能
最初に信託を組成する段階において、後から変更が必要ないように決めておけば、変更手続きなどの負担を減らせます。
信託契約の変更手続きは、法的な知識や、課税関連の確認・注意が必要となるためです。
「受託者に何かあった場合は?」「自宅不動産を売却や賃貸することになった場合は?」など、起こりうる事態を当初から想定して契約書を作成するのがおすすめです。
ただし、変更の可能性まで見据えて契約内容を決めていくことは簡単ではありません。
この場合は家族信託の専門家に相談することで、設計を工夫し、リスクや変更手続きの手間を最低限にできる可能性が高まります。
信託契約の契約内容を変更する方法(信託法に沿って)
信託契約の内容の変更については、信託法に規定があります。
様々なパターンがありますが、ここでは3つのパターンについて、解説していきます。
- 「委託者、受託者及び受益者」の合意による変更(信託法第149条第1号)
- 「受託者及び受益者」の合意による変更(信託法第149条第2項第1号)
- 信託法の規定にかかわらず、信託契約で定めた方法による変更(信託法第149条第4項)
1.「委託者、受託者及び受益者」の合意による変更(信託法第149条第1項)
委託者、受託者、受益者の3者が合意することで、信託契約を変更する方法です。
家族信託では一般的に、契約締結当初は「委託者=受益者」となるため、実質的には「委託者兼受益者(主に親)」と「受託者(主に子)」の2名の合意によって、信託契約の内容を変更します。
家族信託の変更は原則この方法で行われます。
2.「受託者及び受益者」の合意による変更(信託法第149条第2項第1号)
「信託の目的に反しないことが明らかであるとき」には、「受託者及び受益者の合意」で信託の変更を行うことが可能です。
なお「信託の目的に反しないことが明らかであるかどうか」については、信託の変更内容や変更による影響を、信託の目的や趣旨、受益者の利益、契約条項との整合性などと照らし合わせて判断することになります。
3.信託法の規定にかかわらず、信託契約で定めた方法による変更(信託法第149条第4項)
信託契約の中で変更方法を具体的に定めた場合には、その方法により変更を行うことが可能です。
設計の自由度が高いという信託の特徴を活かした方法だといえるでしょう。
ただし、契約内容の変更時には大きな注意点が2つあります。
注意点1.信託の変更には「委託者の意思能力」が必要
信託の契約内容の変更においては、基本的に信託契約の当事者(委託者、受託者及び受益者)の合意が必要となります。
しかし、契約内容の変更時において、委託者の判断能力が低下していた場合、変更の合意をすることができず、変更そのものができなくなるリスクがあります。
家族信託では、高齢の方が委託者(兼受益者)となるケースが多く、契約内容の変更時には認知症などで判断能力が低下しており、変更の合意ができないといったことは十分にあり得えます。
この問題については、上記[2]のように、委託者以外の人員で契約内容の変更合意をする方法を取ることで対処可能です。
例えば、「契約内容の変更には、受託者及び受益者の合意を要する」と定めておけば、受託者と受益の二者のみで変更が可能となります。
委託者の地位は代理できない
仮に、受託者にもしものことがあれば、後継受託者が就任することができます。受益者についても「受益者代理人」を指定できるため対処可能です。
このように、受託者と受益者についてはもしもの際の対応方法がありますが、委託者(もともとの資産保有者)の地位については代理人の設定はありません。
委託者に代わって合意をする者を指名することはできないのです。財産保有者の地位について、一種の保護策を設けている状態だといえます。
このような理由から、契約内容の変更時に委託者の判断能力が低下していた場合、変更の合意をすることができず、家族にとっては変更そのものができなくなるリスクになるケースがあるのです。
委託者の明確な合意なく、後からむやみに信託契約を変更できない規制のようになっています。
このように委託者の意思能力については家族信託において重要な前提条件となっているのです。
注意点2.「特定委託者」への該当により受託者へ贈与税の課税リスクがある
では、上記の【1】をクリアすれば、信託契約の内容は全体的に変更可能なのでしょうか。
現実的ではありませんが、実際にその合意が得られれば変更可能です。
ただし、とくに信託契約を全体的に変える際には、「受託者が特定委託者に該当する可能性」を検討し、課税のリスクはないか確認しておく必要があります。
信託契約を大きく変えようとする場合、受託者の権限を拡充する可能性が高く、そうなると「受託者が特定委託者に該当する可能性」が高まるからです。
また、これから信託契約を組成する場合も、この「特定委託者」について留意しましょう。特定委託者の課税リスクと課税を回避する信託契約の構成について説明します。
特定委託者に該当する「受託者」とは
名称は「特定委託者」ですが、信託契約の「受託者」について一定の定めがあります。
下記の2項目に該当するかどうかで、「その受託者は特定委託者に該当する」が判断され、信託の契約時に贈与税が課税される可能性があります。(相続税法9条の2 1項、5項)
- 他の者との合意などにより信託の変更をする権限を現に有している
- 信託終了により信託財産を取得することになっている
一般的な家族信託では、受託者は信託財産についての権限を当然有しています。また、委託者が死亡するなどの相続が発生したら、信託財産を相続することになるでしょう。
これでは「受託者」役を引き受けている大半の親族は、「特定委託者」に該当してしまうのではないでしょうか。
つまり、家族信託では資産の権限が移動するため、基本的に贈与税の課税リスクがあるということになります。
ただし、その課税リスクを避けるため一定の契約内容を盛り込むことで、受託者の課税リスクは回避可能です。
その回避文言と、このような規定が設けられている理由について、もう少し見ていきましょう。
課税リスクを回避する契約条項とは
課税されるリスクを避けるためには、受託者に与えられている「信託の変更権限には制限があり、一定の範囲に抑えられている」ことを信託契約に明記しておく方法を取ります。
受託者に与えられている信託の変更権限が「軽微な変更をする権限として、信託の目的に反しないことが明らかな場合」には、「特定委託者」に該当しないからです。
その場合、贈与税が課税されるリスクもありません。
そのため、実務上は、受託者の信託の変更権限を「本信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り」と限定して定めます。
このように明記することで、特定委託者への該当を回避します。
なぜ「受託者」を「特定委託者」と呼ぶのか
この規定では、信託契約で受託者が過剰な権限を持つのを抑える主旨もあるといえます。
受託者でありながら、特定「委託者」と規定されているのは、受託者の権限が大きくなると、もはや委託者(兼受益者)と実質的に変わらない権限になると指摘しています。
- 信託資産に大きな権限を有するなら、もはや受託者とはいえない(特定委託者として指定)
- 条件に該当する場合、「みなし贈与の課税対象」とする
という流れです。
そのため一般的な家族信託では、課税を回避する条文を盛り込んで受託者への課税リスクを避けるようにします。
そして信託契約の通り、受託者は契約の範囲内で資産管理を行うことになります。
この特定委託者の規定は、受託者への過剰な権限譲渡が行われないよう防ぐための壁になっているといえるでしょう。
まとめ
信託契約後に契約内容を変更するための方法や注意点についてお伝えしてきました。
最後にもう一度、ポイントを見直しておきましょう。
ポイント①
合意が必要な者を定める際に、委託者の意思能力低下リスクに備えるため、合意者から委託者を除く方法もある
ポイント②
特定委託者課税を回避するため、受託者は「本信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り」契約内容の変更ができるという主旨の範囲で変更権限を限定する
このように留意することで契約内容を変更することが可能です。
変更する際には、変更する箇所と変更後の内容などを明記した「合意書」を作成し、合意する者同士が記名押印をして作成します。信託契約書の原本と共に保管するようにしましょう。
ただし上述しましたが、最も大事なのは信託を組成する最初の段階で後のことを想定し、変更が不要になるような組成にしておくことです。
先々まで見通した構成は簡単ではありませんが、家族信託を熟知した専門家に相談の上、できるだけ変更が不要となる組成を検討していきましょう。
家族信託について、専門家に相談する際は専門家選びも重要なポイントとなります。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する