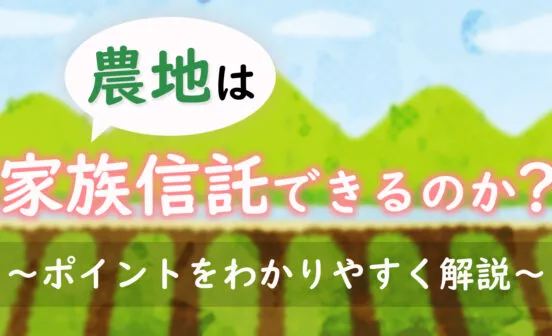家族信託は、認知症による資産凍結対策として、高齢の親御様が元気なうちに資産の管理や運用を家族へ託しておく制度です。
信託される主な財産には、預貯金や土地・建物などの不動産、有価証券などがあります。
ただし、「農地」を所有し、信託を検討している場合は注意が必要です。
農地法により「農地」をそのまま信託することは原則できないため、宅地などに変更する「農地転用」の手続きが必要となります。
本記事では「農地の家族信託」をテーマに、詳しく解説していきます。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する
目次
家族信託とは?
家族信託は、委託者(主に親)が受託者(主に子)へ財産の管理や運用を託す制度です。
高齢になり、認知症などで判断能力がなくなると、本人の判断能力が必要な預金の引き出しや不動産の売却などができなくなるリスクがあります。
家族信託では、このような「資産凍結」が起こらないように、親御様が元気なうちから備えておくことができます。
家族信託の仕組みやメリット・デメリットについては、以下の記事でも詳しくまとめていますので、ぜひご覧ください。
家族信託とは?仕組みやメリット・デメリットを専門家がわかりやすく解説
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
親御様が「農地」を所有されている場合、本人がご高齢で今後の管理や売却などの手続きに不安があるという声が多く、信託を検討したいという問い合わせも寄せられます。
では、農地の信託について、詳しくみていきましょう。
原則「農地」は家族信託できない
土地の家族信託を検討している場合、地目が「農地」の場合に注意が必要です。
ではまず「農地」にはどのような土地が該当するのでしょうか。
地目の「農地」とは
地目とは土地の主たる用途による区分を表す名称であり、不動産登記法により土地の謄本の「登記事項証明書」に記載される情報です。
現在は「宅地」「田」「畑」「雑種地」「山林」「原野」など、全部で23種類あります。
この中で「田」「畑」については農地として「農地法」により厳しい制限を受けています。(農地法4条・5条)
現在、農地として登記されている場合には一定の要件を満たしたうえで、市区町村の農業委員会の許可、または届出をしないと、家族信託の対象とすることはできません(農地法3条2項3号)。
地目の確認は「登記情報提供サービス」で
信託財産や親が所有する土地の「地目」については「登記情報提供サービス」等で調べることが可能です。
税務上の農地(田or畑)判定については、現況により「原野」や「雑種地」と判断される可能性もありますが、登記の際は謄本に記載されている「地目」で判断されます。
地目が「田」や「畑」の場合は農地法の許可書が必要となり、農地転用手続きが必要です。
現在の状況が農地であったり、登記簿の地目が田や畑である場合は、まずは役所に相談して、どのような手続きが必要になるのか確認をしておきましょう。
資産に「農地」がある場合の選択肢
農地を家族信託の対象にする場合、農業委員会への手続きが必要であることは上述の通りです。
このような規制があるため、資産に「農地」がある場合の手続きとしては
- 信託財産に含めない
- 農地転用の許可を取った後で信託財産に入れる
このような方法が想定されます。
信託財産に含めない場合は、農地のみを成年後見制度を利用して管理したり、相続が発生するまで留め置く方法もあるでしょう。
農地は家族信託の財産に含めることは出来ませんが、どうしても農地を信託したいという場合には農地転用の必要があります。
ただし許可申請を出しても通るかどうかは不透明です。
また、注意点もありますのでご確認ください。
停止条件付信託契約でスタートする
農地転用許可の判定には、市町村の農業委員会にて数か月を要する可能性があるため、信託契約を早めに進めたい場合は「条件付信託契約」で対応可能です。
家族信託の契約を結ぶ際に、農業委員会の許可を得ることを条件とする方法を取れば、農地を信託の財産に含むことができます。
つまり、将来的に農地を家族信託の財産に含むという「条件」を付けた上で、家族信託の契約を結ぶという方法です。
この場合、農地については条件が成就した時に信託財産となりますので、家族信託契約の当初は農地を除外する形でスタートすることになります。
あくまでも将来の信託を補助的に担保するものなので、その点は正確に認識しておいてください。
注意点1.自覚のない「農地」に注意
農地はそのままでは信託登記をすることができず地目変更の必要がある、という点については、ご理解いただけたかと思います。
しかしよくあるのが、駐車場や資材置き場として利用しているケースなどです。所有者もとくに自覚がなく、ただし登記簿上の地目は「田」や「畑」になっているような土地です。
相続する際は許可など必要ありませんが、家族信託の手続きについては農業委員会の許可と地目の変更が必要です。
このような自身の土地についての情報を確認するには、登記情報を確認する必要があります。
法務局で登記情報証明書の交付を受けたり、「登記情報提供サービス」で調べたり、土地に関する権利証を確認したりしてみましょう。
注意点2.農地が「市街化区域」にあるかどうかで手続きが変わる
ここまで、農地を信託する場合には農業委員会の「許可」が必要となる旨を解説してきました。
しかし、もしその農地の所在区域が「市街化区域」内である場合には、手続きは「許可」ではなく「届出」で足ります。
「許可」と「届出」ではその手続きが異なります。
- 農地転用の「許可」を得る手続き…数か月掛かることも
- 「市街化区域内」の場合…「届出」手続きでOK
「市街化区域」か「市街化調整区域」であるかによって難易度が異なり、もし「市街化区域」であれば手続きも難しくなく、1週間程度で完了する見込みです。
しかし「市街化調整区域」の場合、許可の申請が難しいケースもあるため、行政書士へ依頼するケースが一般的です。
地目が「農地」となっている土地の家族信託を検討する場合には、その土地の所在する地域が「市街化区域内」なのか「市街化調整区域内」なのかという確認も重要です。
注意点3.農地転用許可を受けた後の課税について
信託財産に含めるため農地転用許可を得た場合、宅地としての評価額に固定資産税が課税されます。
毎年1月1日付けの所有者に対して市区町村役所が現況を判断し、4月1日に新年度の土地評価証明額が確定するため、5月1日に納付書が発送されます。
農転により固定資産税は上がるため、納税費用の準備に注意しましょう。
農地を売却する場合
農地の所有に困り、委託者の存命中に売却しようかという話になるケースもあるでしょう。
ただし、登記上「農地」の場合、原則として一定の要件を満たした農家にしか売れないため、買い手を見つけるのは容易ではありません。自分たちで勝手に売買できず、やはり農業委員会による許可等が必要となります。
そのため農地転用が完了してから売却という流れが一般的です。
農業委員会で転用の許可申請は個人でも可能ですが、複雑な書類も多いため専門家に手続きを依頼する方法が一般的です。
その他の信託財産の取り扱いや信託契約の内容も含め、ぜひ専門家へご相談ください。
まとめ
家族信託は、家庭裁判所を通す成年後見制度に比べると利用しやすい制度です。
但し、資産に農地が含まれる場合には対応方法に注意が必要となります。
登記事項証明書を確認して、登記上の「地目」が農地となっている場合には、現況にかかわらず農地転用のための許可を受ける必要があります。
宅地に転用するか、相続を待つか、他の制度を利用するか、資産状況により適した方法を探す必要があります。ご家族にとってどのような方法が適しているか、信託契約の組成も含めて家族信託の専門家へぜひご相談ください。
家族信託をご検討中の方へ

家族信託の「おやとこ」では、
無料相談を受付中です。
「我が家の場合はどうするべき?」
「具体的に何をしたら良い?」
などお気軽にご相談ください。
年間数千件のご相談に対応中。 サービス満足度96%の「おやとこ」が真心を込めて丁寧にご対応します。
 無料で相談する
無料で相談する