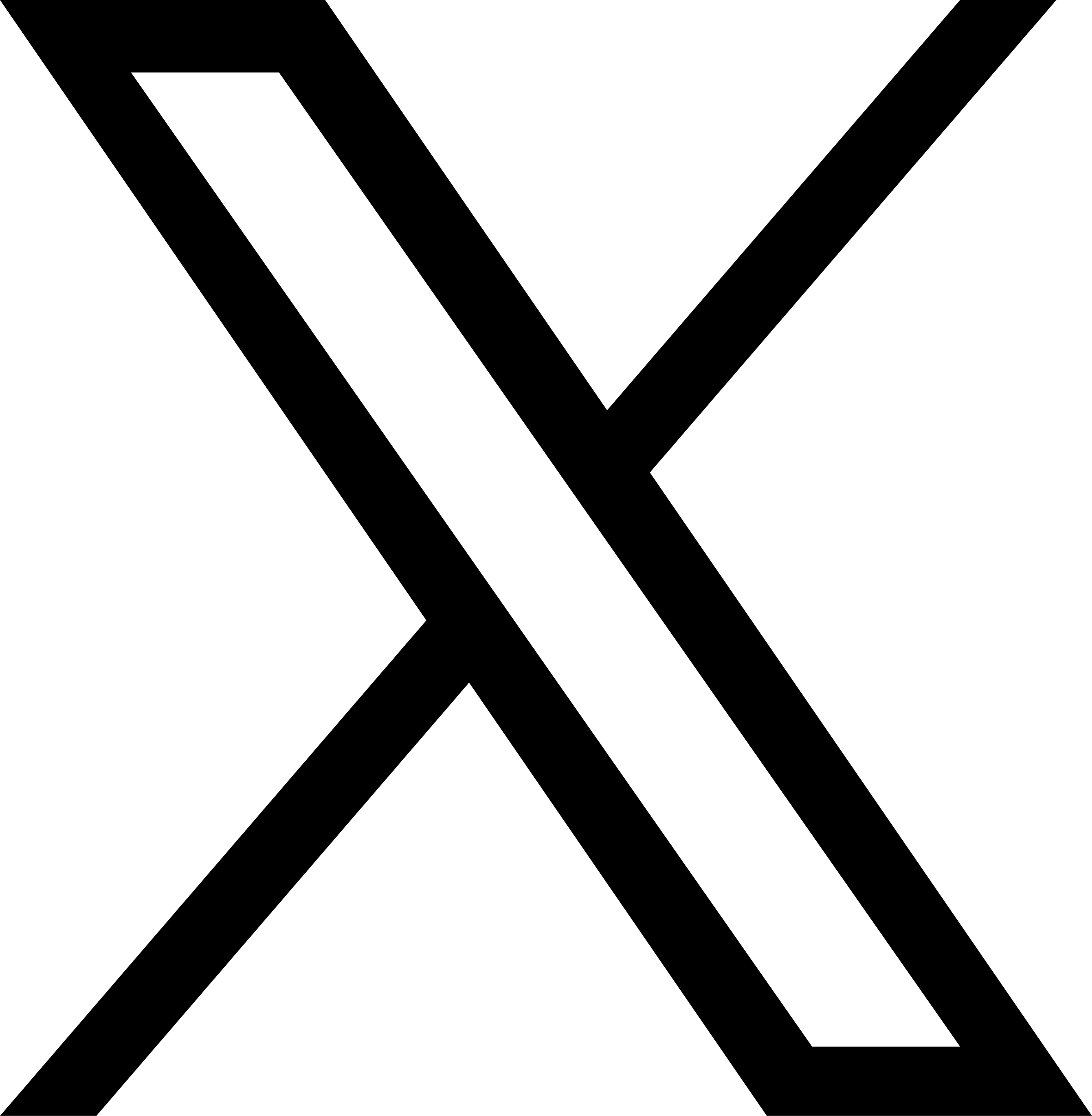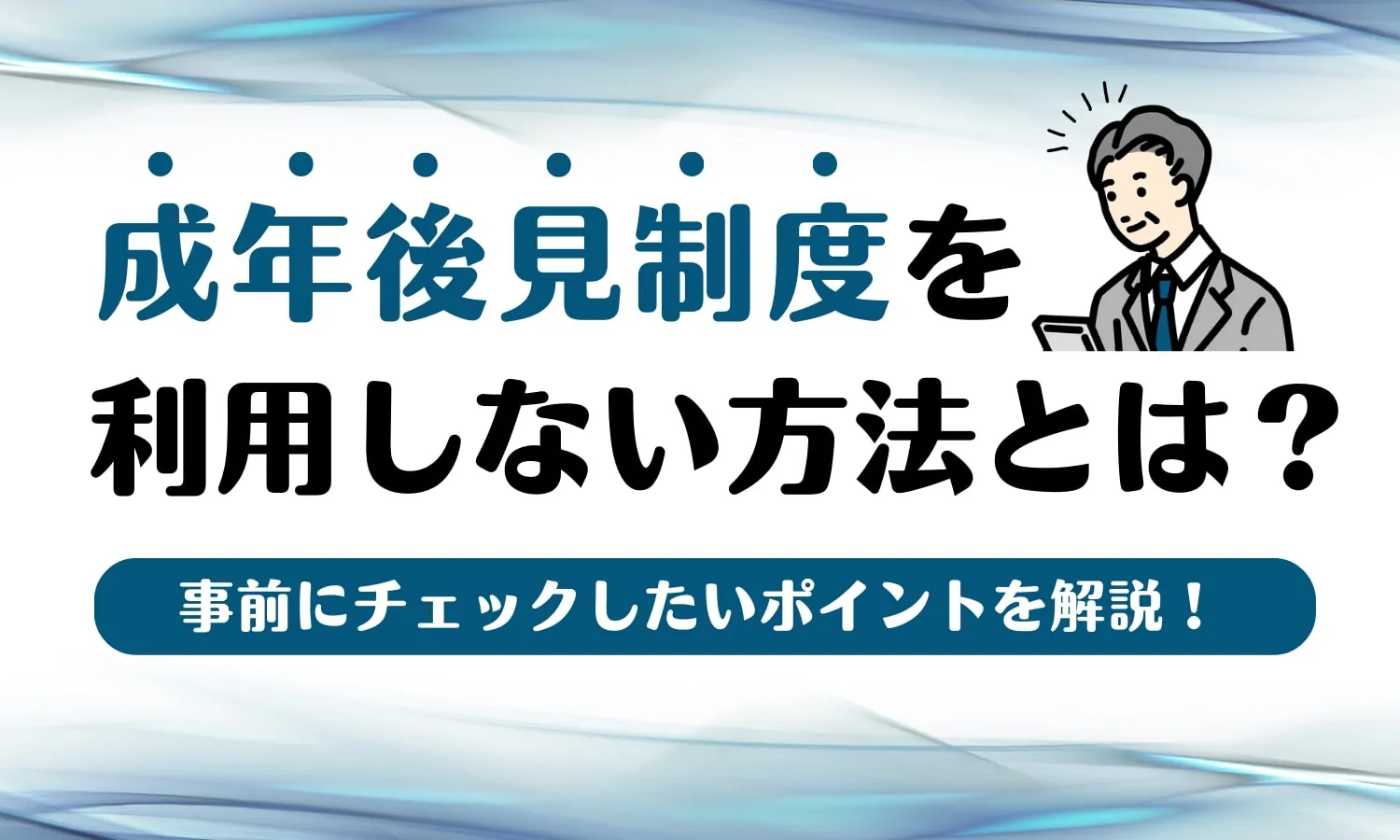成年後見制度は、認知症などで判断能力をなくした方の財産管理や日常生活を援助するための制度です。
成年後見制度についてネットで検索してみると、
「弁護士や司法書士へ払う報酬が高い」
「一度始めたらやめられない」
「家庭裁判所が関与する」
などの懸念点が見つかり、費用や親族の負担について不安に思われる方も多いでしょう。
筆者自身、弁護士として成年後見人の職務を行っていますが、実際は成年後見制度の利用は最終手段となることがほとんど です。
認知症対策・相続対策には早い段階で、より柔軟な他の制度を活用することをおすすめします。
この記事では、親が認知症になって意思能力をなくし、預貯金が引き出せなくなる等の「資産凍結」に陥らないよう、ご家族が事前に行うべき認知症対策・相続対策について詳しく解説していきます。
成年後見制度でお悩みの方へ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。
認知症に完全になる前であれば、任意後見や家族信託など、他の制度を選択することもできます。費用や各制度のデメリットなど、専門家と相談し慎重に決めることをおすすめします。
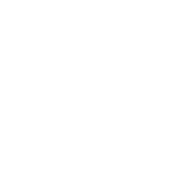 無料で相談する
無料で相談する目次
成年後見制度の問題点
成年後見制度は、認知症などによって判断能力をなくした人を援助するための制度です。
家庭裁判所が選任する「成年後見人」が、本人に代わって財産管理や契約締結などを行います。
成年後見制度を利用すれば、本人の生活や医療・介護などのために本人の財産を動かせるようになり「資産凍結」の状態を解除できます。
本人の預貯金口座から成年後見人が代わりにお金を引き出すことも可能です。
一方で、成年後見制度は、家庭裁判所の監督や許可のもと進めるため、財産管理や処分に大きな制限が加えられる ことが特徴です。
例えば、以下のような例が挙げられます。
成年後見制度による主な制限・デメリット
• 後見人でも自由に本人の預貯金を引き出すことができない
• 本人名義の居住用不動産の売却に家庭裁判所の許可が必要(民法859条の3)
• 後見人に専門家が選任されると、月額報酬が発生する 等
もし、見知らぬ弁護士や司法書士などが後見人に選任された場合、ご家族としては、大事な財産の包括的な管理を第三者に任せることとなり、不安や抵抗感を抱くことも多いです。
また、たとえ親族が後見人となれたとしても、後見人を監督するための後見監督人が選任される場合が多く、やはり弁護士や司法書士などの第三者が財産管理に介入することになるでしょう。
過去には、弁護士や司法書士などの有資格者の後見人による横領事件が度々報じられることもあり、不安は拭いきれません。
筆者は、弁護士として成年後見人の職務も行っていますが、家庭裁判所に対して後見開始の申立てが行われるのは「もうそれしか選択肢がない 」という場合がほとんどです。
成年後見制度を利用する前に、まずは認知症対策や生前の相続対策として、以下で解説する様々な方法を活用することを検討すべきでしょう。
成年後見制度はひどいって本当?7つの問題点と代替制度を完全ガイド
成年後見制度は、認知症や知的障がいなどで判断能力が低下した方々を、不利益や不当な契約から守る制度です。しかし、法的な拘束力が高く「成年後見制度はひどい」と言われることもあるようです。本記事では、成年後見制度がひどいと言われる理由や代わりに使える制度などについて解説していきます。
任意後見制度
上記の成年後見制度は、本人が意思能力を失った段階で、親族や市区町村長などが申立人となり、家庭裁判所が後見人を選任するもの(法定後見制度)です。
一方で、任意後見制度は、本人の意思能力が十分にある段階で、あらかじめ本人が親族などを「任意後見受任者」として、公正証書で「任意後見契約」を結んでおきます。
そして、本人の判断能力が不十分となったときに、受任者が「任意後見人」となって本人を援助するという特別法(任意後見法)上の制度です。
任意後見制度の3つの形態
任意後見制度を利用する場合、次の3つの形態があります。
1.移行型:①任意代理の委任契約(財産管理等委任契約)+②任意後見契約
これは、本人の判断能力が低下する前の段階から、あらかじめ①によって財産管理や身上監護を親族などの受任者に委託しておき、本人の判断能力が低下した後は、①から②に移行させるという形態です。
2.将来型:②任意後見契約のみ
上記①を締結せず、②の「任意後見契約」のみを締結する形態です。
3.即効型:任意後見契約の締結後すぐに、家庭裁判所に対して「任意後見監督人の選任申立て」を行うものです。
本人の判断能力低下が既に生じている場合にこの方法をとることが考えられます。
ただし、判断能力が低下している本人との間で任意後見契約を締結してよいのか(契約締結に必要な意思能力があるのかどうかなど)という問題点が発生します。
そのため、本人の判断能力が低下していると疑われるのであれば、法定後見制度の利用を検討すべきです。
任意後見制度のメリット
ここでは、任意後見制度のメリットを解説します。
メリット1:本人が希望する人物を後見人とすることができる
本人に判断能力が十分あるうちに、自分が希望する親族などを後見人に指定し、任意後見契約を結ぶことができます。
メリット2:本人の居住用不動産を処分(売却)する際、家庭裁判所の許可は不要
法定後見制度の場合は、本人名義の居住用不動産の処分に家庭裁判所の許可が必要ですが、任意後見制度では不要です。
メリット3:本人が支配株主として所有する株式を、管理対象財産に含めるかどうかを選択できる
本人が会社経営者の場合(特に、代表取締役かつ支配株主として、会社を所有かつ経営している場合)、上述の①任意代理の委任契約・②任意後見契約において、その支配株式も管理対象財産に含めるかを決めておくことができます。
支配株式が管理対象財産に含まれている場合は、任意後見人が議決権を行使でき、含まれていない場合、任意後見人は議決権を行使できません。
メリット4:本人の判断能力がなくなり被後見人となっても、取締役の地位を失うことはない
本人が会社の取締役である場合、法定後見制度では、本人が「成年被後見人」になると会社との取締役委任契約が終了(民法653条3号)し、取締役の地位を失います。
しかし、任意後見制度では、本人が判断能力を失い被後見人となったとしても、委任契約は終了せず取締役の地位を失うことはありません。
メリット5:任意後見人に本人の死後事務を委任する旨の特約(死後事務委任契約)を設けられる
法定後見制度の場合、本人が死亡すると後見人の代理権は消滅し(民法111条1項1号)、後見人の職務は終了しますので、その後の本人の財産処理は相続人に委ねられます。
一方で、任意後見制度の場合、任意後見人に死後事務を委任する旨の特約(死後事務委任契約)を設けておくことが可能です。
死後事務委任契約により、任意後見人に本人死亡後に残った債務の清算等を任せることができます。
このように、任意後見制度では、法定後見制度が適用される場合よりも、柔軟な対応が可能 といえます。
任意後見制度の問題点
任意後見契約の効力が生じるのは、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時からとなっています(任意後見法2条1号)。
任意後見監督人にも、弁護士や司法書士などの有資格者が選任されることにより、報酬の支払いが必要となり、成年後見制度と同様に費用の問題が発生してしまいます。
また、本人の自己決定を尊重する観点から、後見制度を利用する場合、法定後見よりも任意後見が優先されます。
しかし、本人の利益のために特に必要があると認められるとき(任意後見法10条1項)には、より制限が強い成年後見等の法定後見に移行することになります。
成年後見人になれる人とは?家族が後見人になる方法を解説
成年後見制度の利用を検討している方は、成年後見人はどんな人がなるのか、家族はなれるのか、といった疑問を抱くケースも多いでしょう。本記事では、成年後見人になれる人の条件や家族が就任する方法、家族が成年後見人になるメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。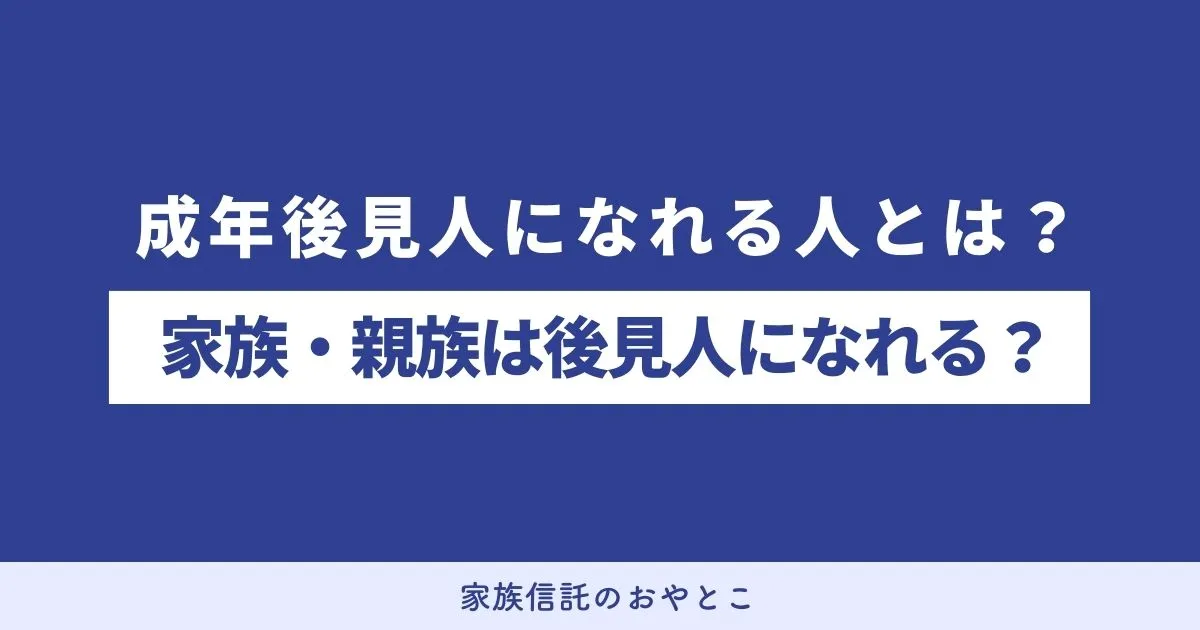
財産管理等委任契約
後見制度を用いずに、財産を管理することを希望する場合には、財産管理等委任契約の利用も検討することができます。
これは、任意後見制度の項で解説した「1. 移行型」の①の契約のみを締結するという方法です。
「任意後見監督人に報酬を支払ってまで任意後見制度を利用することは望まない」という場合でも、本人の死後に受任者と他の共同相続人との間で、預貯金の引き出しなどをめぐる法的紛争に発展すること避けるために行います。
本人の財産管理等の委任(準委任)だけは書面でしっかりと定めておけるという観点で、十分に意味がある といえます。
財産管理等委任契約では、生前の財産管理や身上監護だけでなく、死後事務委任契約もセットで結んでおくと、本人の死後に残された債務の清算等に関する事務も受任者に任せられます。
ここで、任意後見契約も財産管理等委任契約も、何の契約書も交わしていない状態を想定してみましょう。
高齢や身体障害などにより、自分自身での預貯金の引き出しが困難な本人に代わり、同居する特定の親族が預貯金の引き出しを行っていたとしたら、どのようなリスクが想定されるでしょうか。
親族間の人間関係が良好でない場合、本人が死亡して相続が開始すると、他の共同相続人から「無断で被相続人(本人)の預貯金を引き出して消費した」などと主張されるリスクがあります。
さらに、不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求がなされると、多くの場合、訴訟による解決しか方法がありません。
「被相続人(本人)から口頭で包括的な財産管理を任されていた」という場合、訴訟では毎回の引き出し行為と、そのお金の使途(何に使ったか)の主張・立証が必要となります。
こうなれば、多大な労力、時間、費用がかかるうえに、十分な立証ができなければ他の相続人に対し金銭の支払義務を負うことにもなりかねません。
このような法的紛争を予防するため、少なくとも財産管理等委任契約だけは、書面で(できる限り公証役場で公正証書を作成することにより)交わしておくことを強くおすすめします 。
生前贈与
ここまでで述べた制度や方法は、いずれも本人の財産権を受任者や親族に移転せずに、本人の財産を管理・処分するものです。
これらに対し、本人が自らの意思で財産を移転させる方法の一つとして、生前の贈与契約 (民法549条)があります。
例えば、親が現金など自分の財産の一部を子に贈与しておけば、子はその財産を利用して親の介護や日常生活に要する費用を支出することも可能です。
ただし、贈与を受けた人の生活費を援助する目的などの場合には、相続開始後に「特別受益」として、相続分の前渡しを受けたものとみなされます(民法903条1項)。
この場合、贈与を受けた人は、遺産分割時に取得できる遺産が少なくなることがあるため、注意が必要です。
暦年課税と相続時精算課税
生前贈与を行う場合、贈与税に注意する必要があります。
特に、本人が経営者であり、事業承継対策を含めて生前贈与を検討する場合、専門知識を持つ税理士に依頼して進めていくべきです。
※事業承継税制において、特例措置による特例承継計画の提出期限は令和6年〔2024年〕3月31日までとなっています。
一般の生前贈与を行う場合も、1年間に贈与を受けた額が110万円(基礎控除額)を超える場合は、贈与を受けた人に贈与税の負担が発生し、この制度を「暦年課税」といいます。
暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残額について、贈与税額が計算されます。
また、相続時精算課税制度は、60歳以上の親などから18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)の子や孫などに対する贈与を対象とした制度です。
原則として贈与財産から特別控除額2500万円を控除した残額に20%の税率で贈与税額が計算されます。そして、相続時に相続財産の価額も合算したうえで、相続税として納付するという制度です。
(令和5年度税制改正大綱により、令和6年〔2024年〕1月1日以降の贈与より、特別控除額とは別に年間110万円の基礎控除が新設されました。)。
暦年課税と相続時精算課税のいずれを選択するかは、具体的な事情に応じて税務上の様々なメリットやデメリットを考慮して決める必要がありますので、税理士に相談することをおすすめします。
遺言
生前の相続対策という観点からは、遺言書を作成しておくことも大変重要です。
将来、本人が認知症になって成年後見制度を利用することになる場合であっても、意思能力が問題なく認められる段階で本人が遺言書を作成しておくと、相続時の親族間における「争続」を防止できます。
遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。
公正証書遺言は、公証役場で作成し保管されるものです。
自筆証書遺言は、本人が自筆で作成するものですが、法務局に遺言書を保管してもらう「遺言書保管制度」を利用することができます。
遺言書保管制度を利用した場合「相続開始時に他の相続人に遺言書があることを通知してもらえる」「家庭裁判所における検認手続が不要となる」などのメリットがあります。
家族信託
生前に財産権を移転させるもう一つの方法として「家族信託」があります。
認知症発症に伴う資産凍結や制限が多い成年後見制度と異なり、家族の財産を家族で管理する方法として、近年非常に注目されています 。
家族信託のメリット
家族信託は、本人(委託者)が、認知症などによって判断能力を失う前に、信頼できる家族(受託者)との間で信託契約を締結し、自らの資産の管理・処分を任せておく制度です。
家族信託においては「委託者」と「受託者」のほかに、信託財産から生じる利益(例:不動産の家賃収入など)を受ける「受益者」が存在します。
しかし、多くの場合は委託者と受益者が同一人物である「自益信託」となります。
自益信託では、委託者の生前は委託者本人が収益(信託財産から生じる利益)を取得しつつ、財産管理自体は家族に委ねられる上に、贈与税の課税も回避できるという大きなメリットがあります。
家族信託における2つの形態
家族信託には、大きく分けて次の2つの形態があります。
1.遺言代用型信託
委託者兼受益者の死亡により信託契約が終了し、信託財産(残余財産)を相続人等の「帰属権利者」に承継させる形態です。
つまり、本人が死亡して信託契約が終了したあとに、残された本人の財産の承継先を、信託契約の中で「帰属権利者」として指定おくことで、本人の死後は実質遺言と同様の機能を果たします。
これにより、家族信託が遺言を代用する機能が生ずるということです。
2.受益者連続型信託
委託者兼受益者の死亡によっても信託契約を終了させず、信託受益権を相続人等に連続して引き継がせていく形態です(信託法91条)。
信託契約の中で、本人の死後の信託財産の受益権を、子供や孫などに連続して承継させていく際に利用されます。
いずれの形態を採る場合でも、信託契約の組成に当たっては、誰を受託者とし、どの財産を対象とするか、また、相続開始後の遺留分侵害額請求(民法1046条)の可能性や税務上の問題点等、様々な観点からの検討が必要となります。
家族信託とは?メリット・デメリットや手続きをわかりやすく解説!
家族信託は「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みです。本記事では家族信託の詳細や具体的なメリット・デメリット、発生する費用などについて詳しく解説します。将来認知症を発症しても、親子ともに安心できる未来を実現しましょう。
まとめ
以上、成年後見制度を使わずに、親の認知症による資産凍結を防ぐ方法を解説しました。
それぞれの制度に、メリット・デメリットや、使いどころがあります。
いずれの制度を使うにせよ、まずは専門家に相談し、適切な助言を受けて手続を進めることをおすすめします。
成年後見制度でお悩みの方へ

成年後見制度では、財産の柔軟な管理ができない、家族が後見人になれない、専門家への報酬が高いなど、さまざまな課題があります。
認知症に完全になる前であれば、任意後見や家族信託など、他の制度を選択することもできます。費用や各制度のデメリットなど、専門家と相談し慎重に決めることをおすすめします。
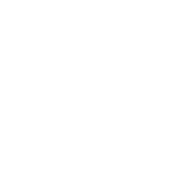 無料で相談する
無料で相談する